春分とはいえ、春は名ばかりの肌寒い3月の午後、事務所のドアが静かに開き、50代半ばの女性が丁寧に頭を下げて入ってこられました。鈴木さん(仮名)です。
「先生、私、どうしたらいいのでしょうか…」
疲れた様子で椅子に腰掛けた鈴木さんは、長年にわたる家族の介護と、最近直面している相続問題について話し始めました。
長年の介護と感謝の遺言
鈴木さんのご主人は3人兄弟の長男でしたが、12年前に病気で亡くなりました。それでも鈴木さんは同居していた義母の介護を続け、さらに病弱だった義弟の二郎さん(仮名)の看病も引き受けていました。
「毎日大変でしたが、家族ですからね。当たり前のことをしただけなんです」と鈴木さんは淡々と語りました。
3年前に義母が亡くなり、そして今年1月、長い闘病生活を送っていた二郎さんも息を引き取りました。二郎さんは生涯独身で子供はおらず、両親も兄も既に他界していたため、相続人は末弟の三郎さんだけでした。
二郎さんは鈴木さんの長年の献身に深く感謝していました。そのため、自分の所有する土地建物を鈴木さんに遺贈するという公正証書遺言を残していたのです。
「二郎さんはいつも『姉さんがいなかったら、こんなに長く生きられなかった』と言ってくれて…」鈴木さんの目に涙が浮かびました。
突然の波乱
しかし、二郎さんの死後、それまで疎遠だった三郎さんが突然現れ、相続権を主張し始めたのです。
「最初は遺留分について弁護士に相談したと聞きました。でも兄弟には遺留分はないですよね?」と鈴木さんは不安そうに尋ねました。
私は頷きました。「はい、遺留分があるのは配偶者や子、親だけです。兄弟姉妹には遺留分はありません」
一見、問題なさそうに思えます。公正証書遺言があり、遺留分も問題にならない。鈴木さんは安心して良いのでしょうか?
「実は…」鈴木さんは困惑した表情で続けました。「三郎さんの弁護士から連絡があって、二郎さんの遺言は死亡直前に作られたから無効だと主張しているそうなんです」
公正証書の落とし穴
ここに公正証書遺言の落とし穴があります。確かに公正証書は法的効力が高い文書ですが、その有効性を最終的に判断するのは裁判所です。二郎さんの判断能力や遺言時の状況によっては、遺言の有効性が裁判で争われる可能性があるのです。
さらに重要なのは、遺言があるからといって安心して手続きを後回しにすると、大変なことになりかねないという点です。
「鈴木さん、今、土地建物の名義はどうなっていますか?」と私は尋ねました。
「まだ二郎さん名義のままです…」
私は真剣な表情で説明しました。「これが危険なんです。三郎さんは法定相続人ですから、単独で自分の名義に変更することができてしまいます。遺言があっても、先に登記手続きをされてしまうと、取り戻すのに時間と労力がかかります」
鈴木さんの顔から血の気が引きました。
迅速な行動の重要性
「遺言の効力は遺言者の死亡と同時に発生するので、理論上は三郎さんの登記は無効になります。しかし、実際に裁判で争われると、最終判断が出るまでの間、不動産は三郎さん名義になっている可能性があります」
さらに怖いのは、その間に第三者に売却されてしまうケースです。善意の第三者が介入すると、さらに問題は複雑化します。
「でも…公正証書があれば大丈夫だと思っていました」と鈴木さんは肩を落としました。
「公正証書は確かに強力な証拠ですが、それだけで安心はできません。今すぐに遺贈の登記手続きを進めましょう」
教訓:公正証書があっても迅速な行動を
私はこの経験から、相談者にいつも伝えています。公正証書遺言を作成することは非常に重要ですが、それと同じくらい重要なのは、相続発生後の迅速な手続きです。特に相続人間で争いの可能性がある場合は、一刻も早く登記手続きを進めるべきです。
公正証書があるから大丈夫と安心して手続きを後回しにすれば、せっかくの遺言が台無しになりかねません。遺言者の最後の思いを確実に実現するためには、遺言書の作成だけでなく、相続発生後の適切かつ迅速な対応が不可欠なのです。
鈴木さんの件は、幸い早期に対応できたため、無事に遺贈の登記を完了することができました。しかし、もう少し対応が遅れていたら…と考えると背筋が凍る思いです。
公正証書遺言は強力な法的ツールですが、それを実現するための行動も同じくらい重要だということを、この事例は教えてくれています。
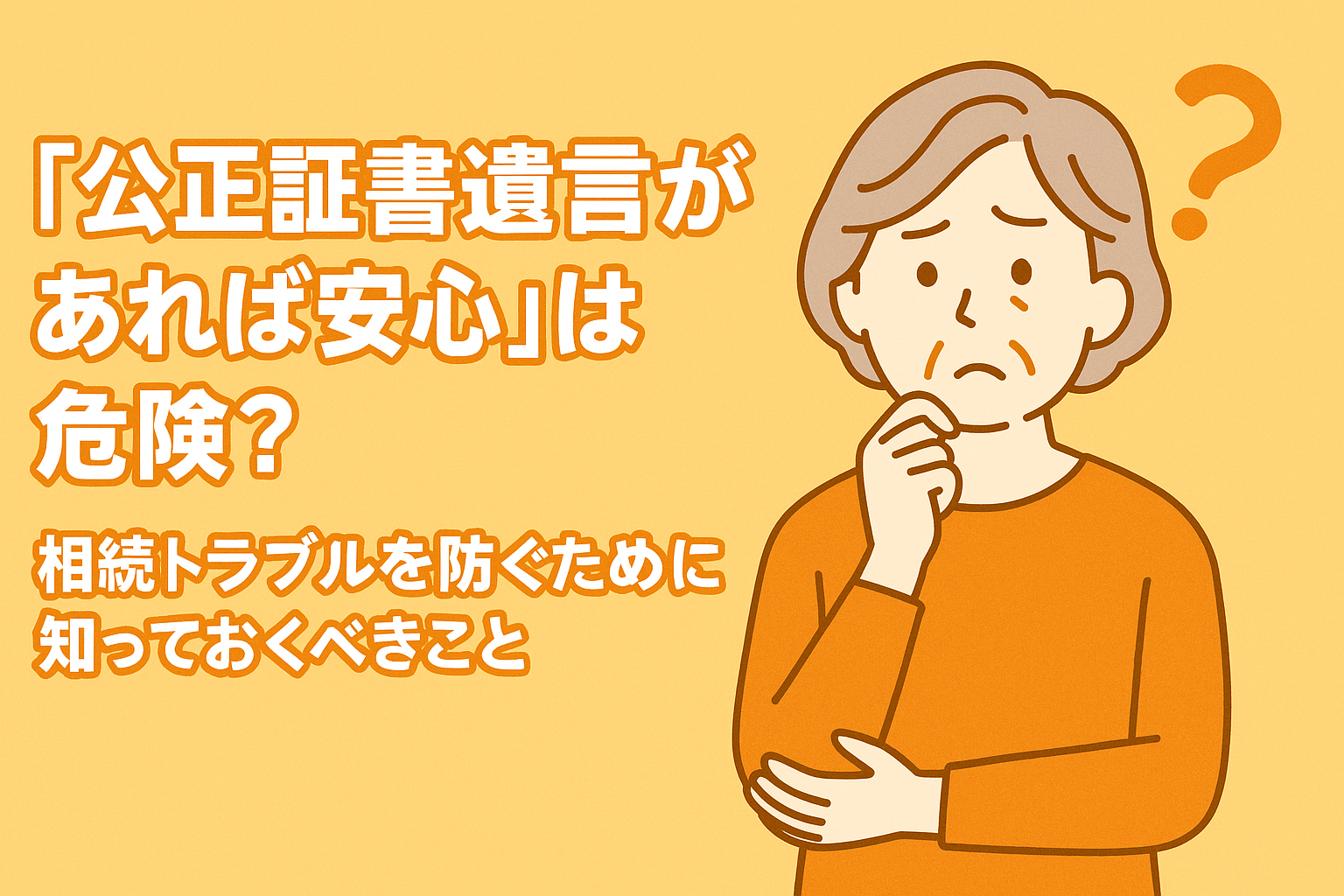
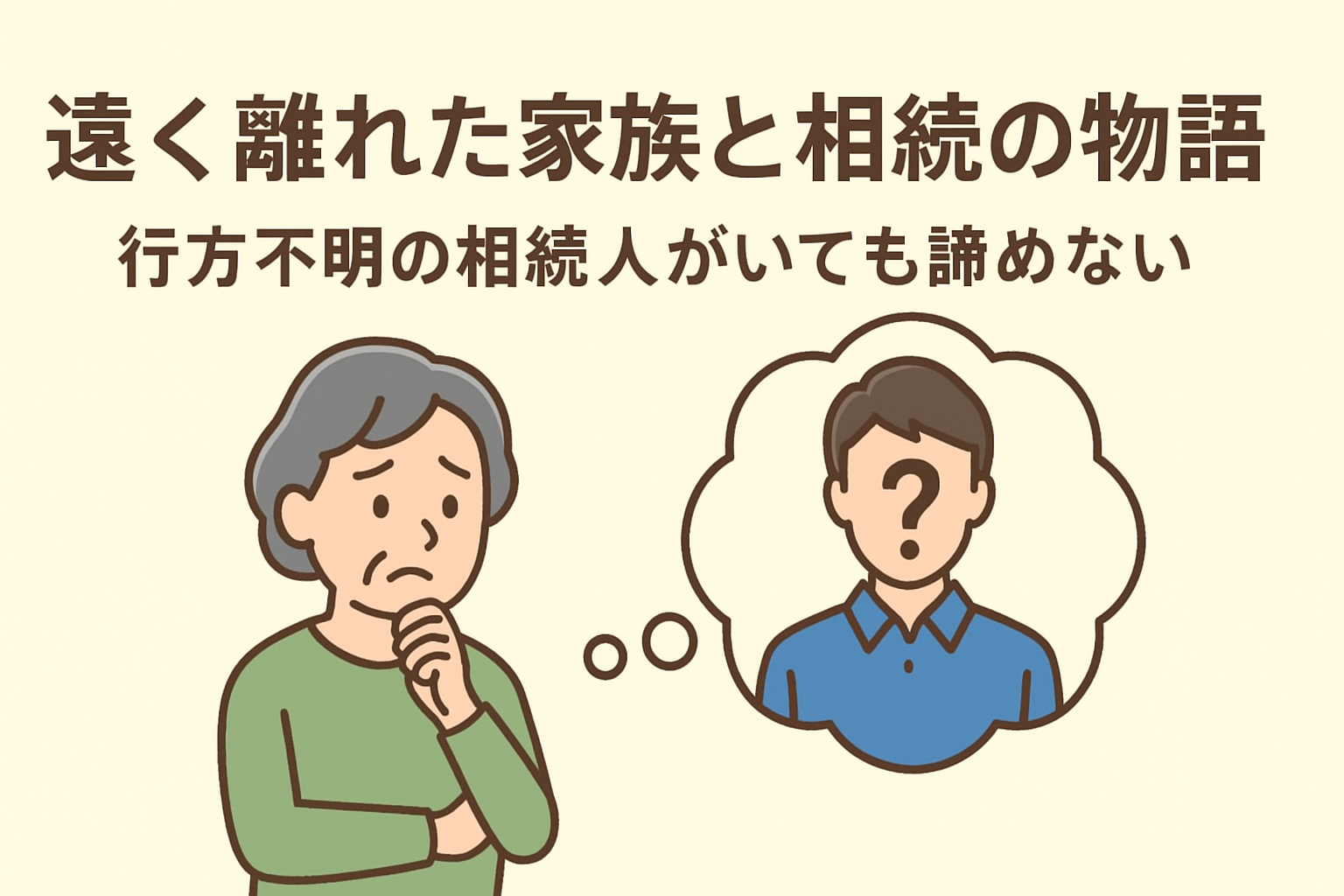
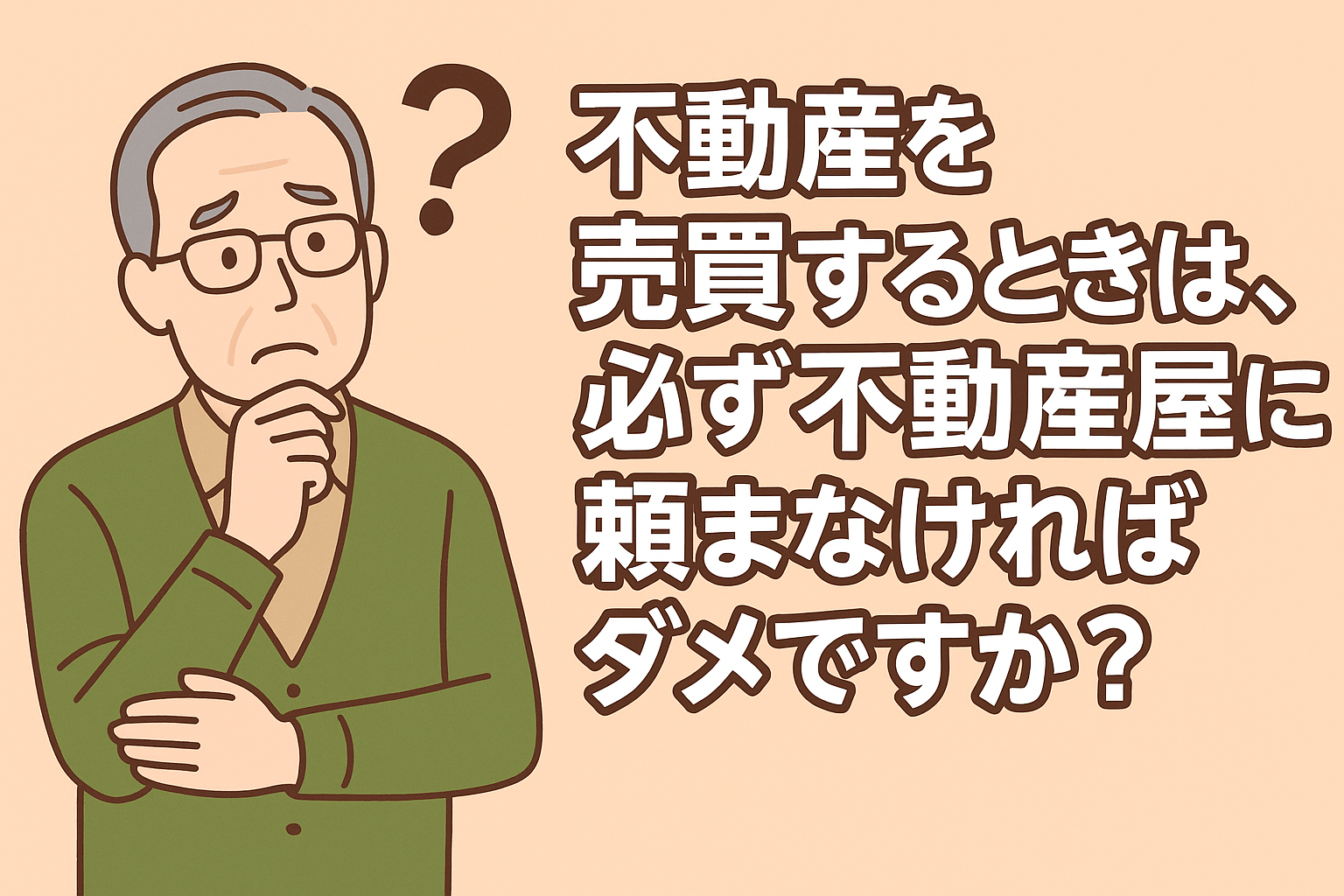
コメント