ある春の日。中堅製造業を営む株式会社テクノロジーズでは、新年度の新入社員を迎える準備に追われていました。採用活動を担当するのは、社長の田中さん、そして長年バックオフィスを支えてきた奥様のAさん。
Aさんが人事や労務の実務を担当しており、今回も新入社員の受け入れを進めていました。
「1ヶ月じゃ見極められない」
実はAさん、以前から気になっていたことがありました。
「最近の新入社員、面接では良く見えても、実際に働き出すと『あれ?』って思うことが増えてきて……。1ヶ月の試用期間じゃ、正直判断が難しいんです。」
そこで田中社長夫妻は、顧問社労士の小椋に相談しました。
「試用期間、3ヶ月に延ばしたいんです。特に問題ありませんよね?」
社労士の小椋は応えました。
「法律上、試用期間の長さは自由に定められます。3ヶ月に延ばすことは可能です。ただし、就業規則の変更として労基署への届出が必要になりますね。」
こうして、テクノロジーズでは正式に試用期間を「3ヶ月」に延長することに。慎重な採用と見極めの体制を整えた……はずでした。
入社3日目の無断欠勤
ところが、就業規則を改定して迎えた新入社員のひとりが、なんと入社3日目で無断欠勤。驚いたAさんが家族に連絡を取ると、こんな答えが返ってきました。
「昨夜、睡眠薬を飲んで起きられなかったらしくて……」
その後も、不安定な出社が続き、報告連絡相談もままならない。社長夫妻は頭を抱えます。
「試用期間中だし、このまま契約を打ち切るしかないか…?」
しかし、ここで社労士の小椋から厳しい現実が告げられます。
試用期間中でも、いつでもクビにできるわけじゃない?
「実は、入社から14日を過ぎると、試用期間中でも解雇には“正当な理由”が必要になります。予告や手続きも必要です。」
「しかも、最高裁の判例では、採用後に明らかになった“新しい事実”で、かつ採用時点では知ることができなかったような事情でないと、試用期間中の解雇は正当とは認められません。」
つまり、見極めに自信がなかったとしても、「とりあえず採用して試用期間で判断する」という姿勢では、リスクを背負うことになるのです。
採用を「慎重に始める」ことが最大のリスクヘッジ
この一件のあと、田中社長とAさんは採用方針を大きく見直しました。
- 面接時には職務理解の確認だけでなく、ストレス耐性や責任感もチェック。
- 書類や面談だけで不安があれば、勇気をもって「見送る」決断を。
- 採用決定後も、入社初期の報連相や出勤状況を丁寧に記録。
「試用期間って、企業が一方的に好きなタイミングで“お試し解除”できるものじゃなかったんですね。採用時点でしっかり判断することの大切さを実感しました。」
今日のポイント
「試用期間があるから大丈夫」ではなく、
「採用前にしっかり見極める」が鉄則。
試用期間とは、単なる「猶予」ではなく、法的な労働契約が成立している期間です。そのなかで適格性を確認するための制度に過ぎません。
企業にとって採用は“未来の投資”。
「入社してから考える」ではなく、「入社させる前に考え抜く」。
それこそが、採用ミスによるトラブルを未然に防ぐ最大の武器なのです。

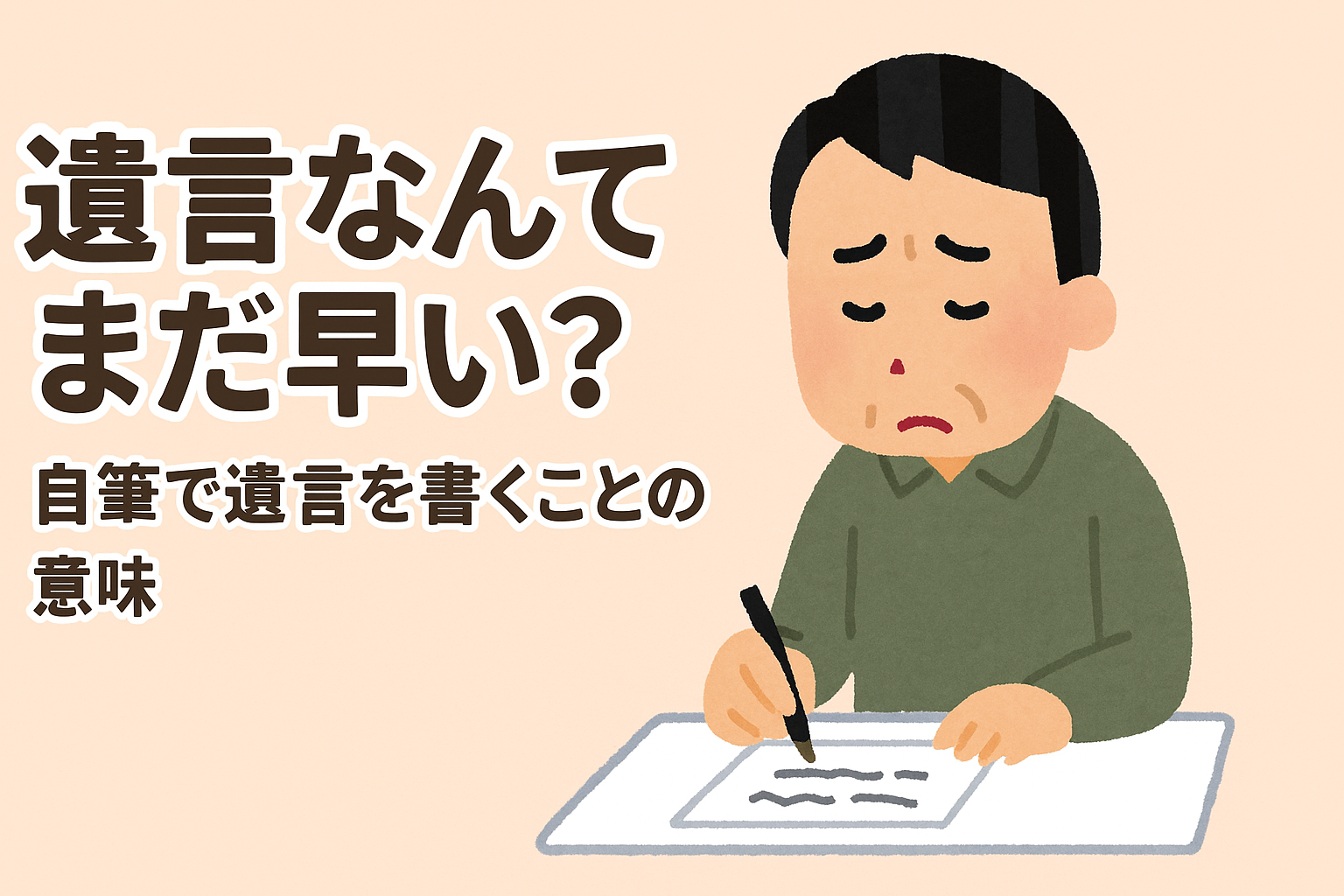
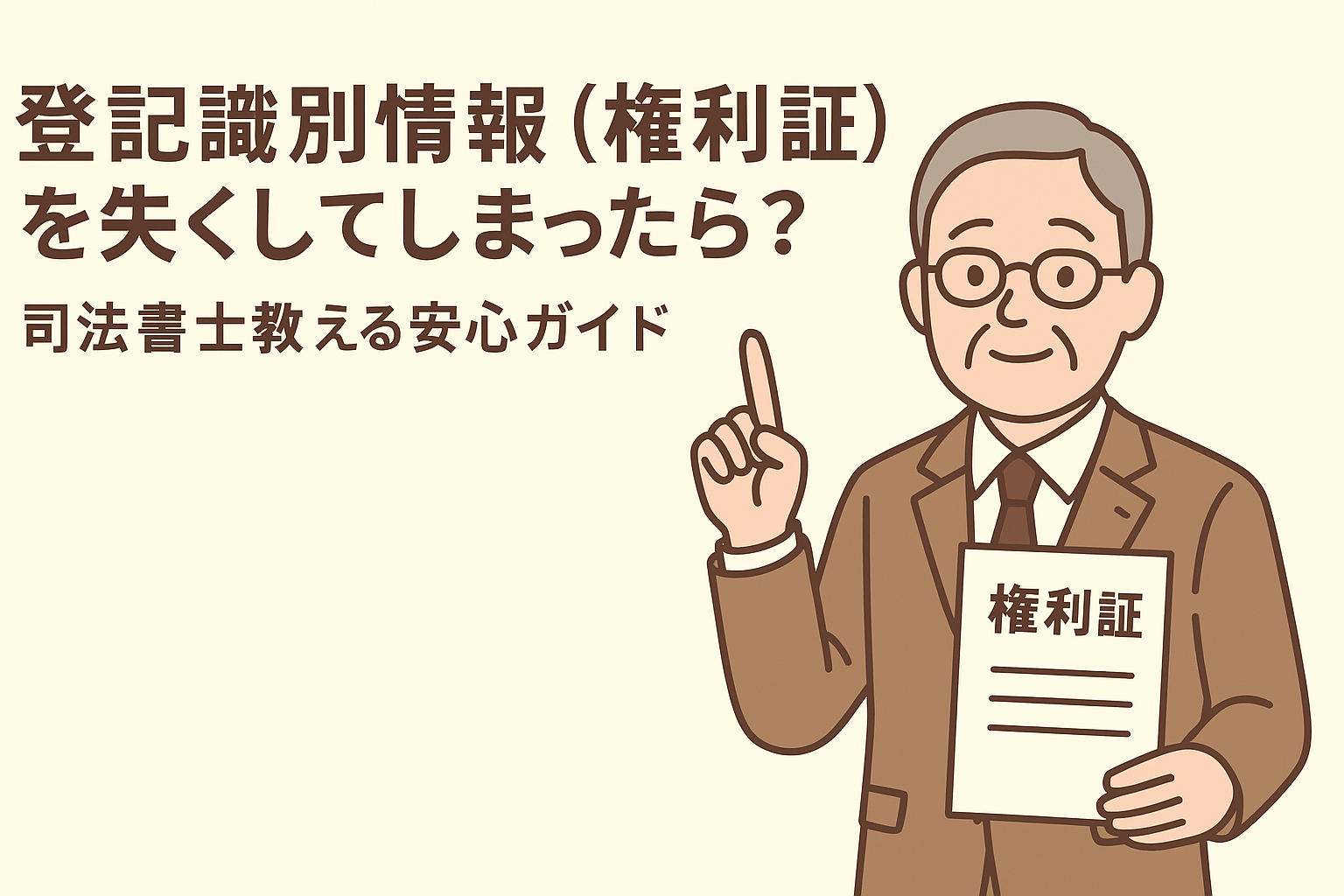
コメント