移住で初めて気づいた”ガス事情”
横浜市鶴見区から湘南エリアへの移住を決めたとき、住居選びで思わぬ壁にぶつかりました。それは「都市ガスを使える住居がとても少ない」という現実でした。
生まれてからずっと都市ガスのエリアに住んでいた私にとって、これは盲点でした。都会育ちの方なら共感していただけるかもしれませんが、ガスといえば「都市ガス」が当たり前だと思っていたのです。しかし、湘南エリアの物件を探し始めると、多くの住居がプロパンガス(LPガス)を使用していることに気づきました。
これをきっかけに、都市ガスとプロパンガスの違いについて真剣に調べ始めたのです。
数字で見る都市ガスとプロパンガスの現実
調べてみると、日本の世帯のガス利用状況は以下のようになっています:
- 都市ガス:約2,700万世帯(全世帯の約46%)
- プロパンガス:約2,200〜2,400万世帯(全世帯の約38〜40%)
- その他(オール電化など):約900万世帯(全世帯の約16%)
都市部に住んでいると気づきにくいですが、実は日本全国ではほぼ半々の割合で都市ガスとプロパンガスが使われているのです。
また、供給エリアを見ると、都市ガスは国土面積のわずか約6%(主に都市部)をカバーしているのに対し、プロパンガスは都市ガスの約20倍のエリアをカバーしています。つまり、都市を離れれば離れるほど、プロパンガスが主流になるわけです。
衝撃の料金差:平塚のアパート体験
湘南エリアへの本格的な移住に備えて、一時的に平塚市内のアパートを借りることになりました。そこで私は初めてプロパンガスのある住居に住むことになったのです。
そして最初のガス料金請求書を見て愕然としました。これまで使っていた都市ガスと比べて、なんと約2.5倍もの料金!同じような使用量なのに、こんなに違うのかと驚きました。
私の場合は極端な例かもしれませんが、一般的にもプロパンガスは都市ガスの約1.7〜1.8倍の料金がかかるとされています。3人家族の場合、都市ガスなら月額約5,000〜6,000円程度ですが、プロパンガスだと約8,500〜10,000円になることも珍しくありません。
プロパンガスはなぜ高いのか?
プロパンガスがこれほど高額になる理由は複数あります:
- 自由料金制:プロパンガスは各会社が自由に料金を設定できます。対して都市ガスは公共料金として規制されています。
- 配送コスト:ガスボンベの配送や交換には人件費やガソリン代などのコストがかかります。
- 設備コスト:ボンベの設置や保守管理にも費用がかかります。
- 競争環境の欠如:特にアパートやマンションでは、入居者がガス会社を選べないケースが多く、競争原理が働きにくいのです。
アパート暮らしの時、私がもっとも困ったのはこの最後の点でした。管理会社との契約で既にガス会社が決められていたため、どれだけ高くても自分で別の業者に変更することができなかったのです。
二宮町での都市ガス生活
幸いなことに、現在住んでいる二宮町の住居は都市ガス(小田原ガス)が使えるエリアでした。湘南エリアでも東京ガスネットワークや小田原ガスなどの都市ガスが供給されているエリアはあります。ただし供給範囲は限られているため、物件探しでは重要なチェックポイントとなりました。
月々のガス代が大幅に下がり、家計的にも助かっています。都市ガスは料金の透明性も高く、急な値上げもないため安心感があります。
都市ガスとプロパンガス、それぞれの特徴
両者には料金以外にも違いがあります:
熱量の違い
- プロパンガス:約24,000kcal/㎥
- 都市ガス:約11,000kcal/㎥
プロパンガスは都市ガスの約2.18倍の熱量があるため、同じ調理時間でも使用量は少なくて済みます。つまり、単純に「使用量×料金単価」で比較すると誤解が生じるので注意が必要です。
それぞれのメリット
都市ガスのメリット:
- 料金が安い
- 安定供給(地下配管)
- 料金の透明性が高い
プロパンガスのメリット:
- 供給範囲が広い(全国どこでも)
- 火力が強い
- 災害時の復旧が早い(個別対応可能)
住居選びで見落としがちなポイント
湘南エリアに限らず、都市部から郊外や地方への移住を考えている方にアドバイスしたいのは、ガスの種類も住居選びの重要な検討要素だということです。
特に長期的に住む予定なら、毎月のランニングコストは大きな差になります。例えば:
- 月々3,000円の差 × 12ヶ月 × 10年 = 360,000円
この金額は決して小さくありません。
また、アパートやマンションの場合は、自分でガス会社を選べるかどうかも確認しておくと良いでしょう。持ち家なら、プロパンガスでも業者選定や交渉の余地があります。
ガスの種類も住居選びの重要ファクター
横浜から湘南への移住を通じて、私が学んだことは「当たり前だと思っていたことが、実は選択肢の一つに過ぎない」ということでした。都市ガスを使える住居が当たり前だと思っていましたが、日本全体で見ればプロパンガスも同じくらい普及しているのです。
移住を考えている方は、家賃や広さ、通勤時間だけでなく、「ガスの種類」も住居選びの判断材料に加えることをおすすめします。特に家計への影響は無視できません。
私は幸運にも都市ガスが使える住居を見つけることができましたが、プロパンガスしか選択肢がない地域も多いのが現実です。その場合は、複数のガス会社から見積もりを取り、適正価格で契約できるよう交渉することも大切です。
小さな気づきが大きな違いを生むことがあります。皆さんの住居選びの参考になれば幸いです。
このブログ記事を読んで、あなたも「住居選びで見落としがちなポイント」について何か気づきがありましたか?コメント欄でぜひシェアしてください。
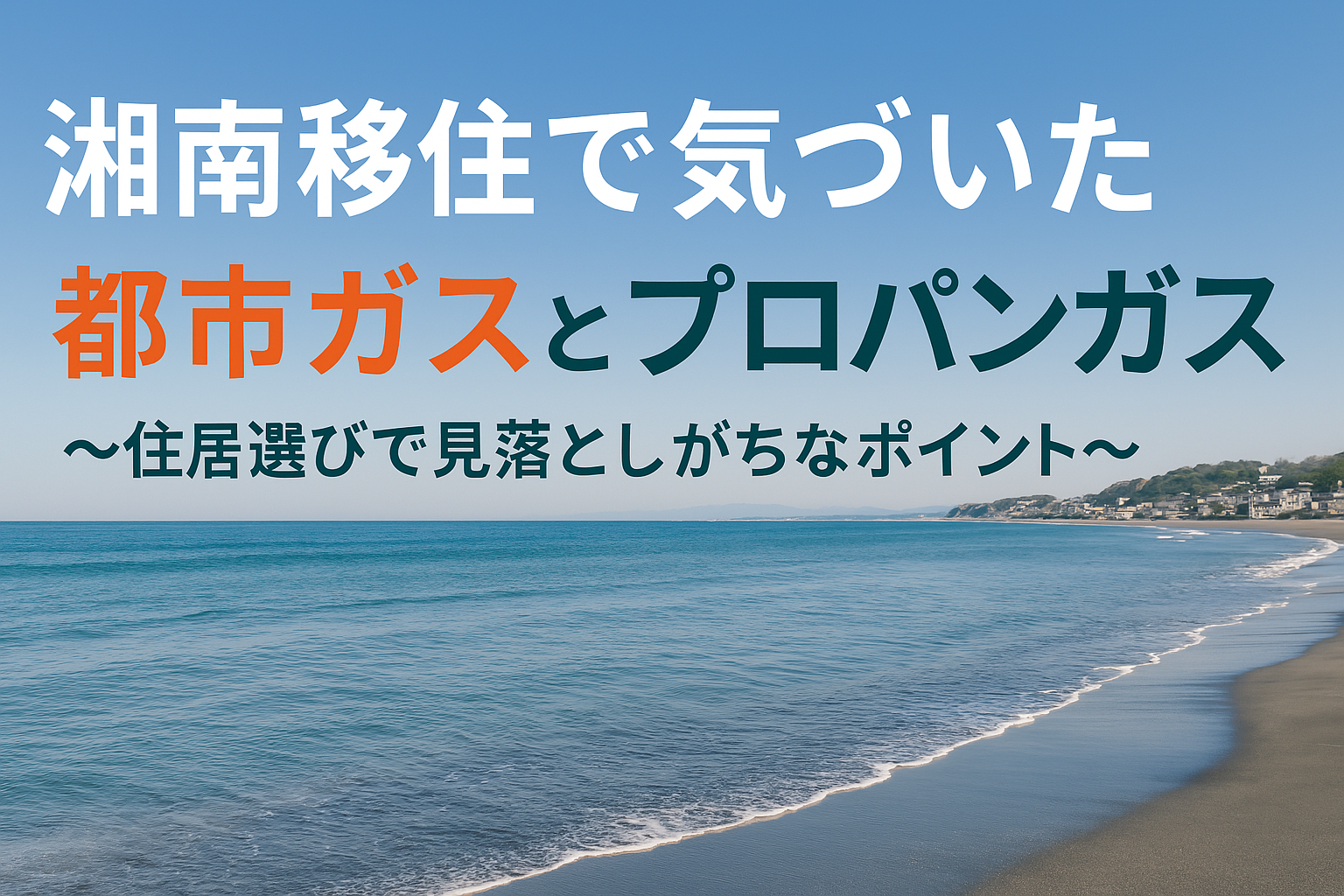

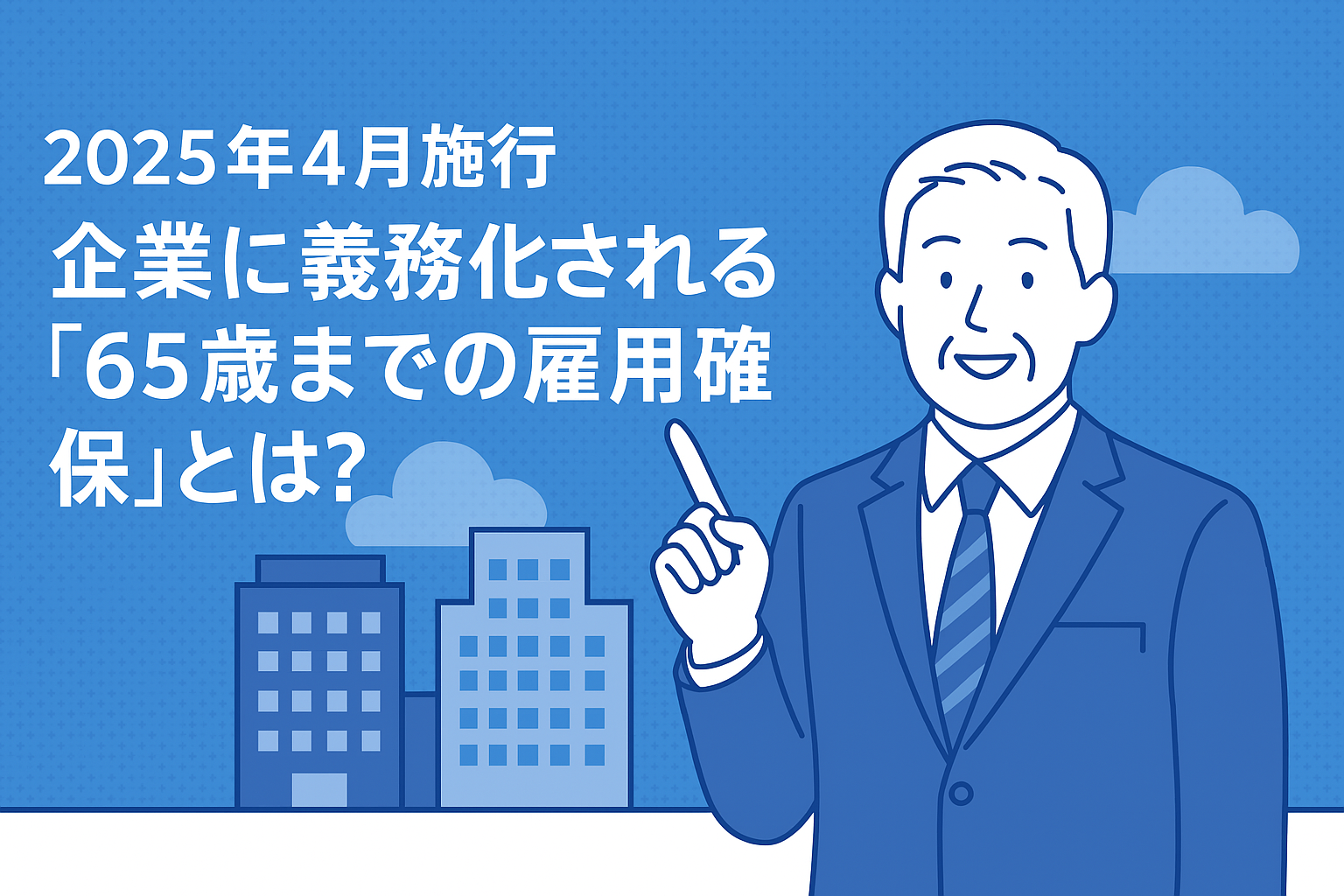
コメント