こんにちは。
司法書士の小椋義雄です。
法律の世界には、日常ではあまり使わない言葉がたくさんあります。
中でも「相続」に関する用語は、意味がとても厳密に決まっていて、
少しの勘違いが大きなトラブルにつながってしまうこともあるんです。
今日は、その代表的な例「相続放棄」について、
実際にあったエピソードを交えながら、わかりやすくご紹介します。
「放棄」って、言葉だけで判断すると危ないんです。
相続が始まると、法律に従って「相続人」が決まります。
- 第1順位:子ども
- 第2順位:親などの直系尊属
- 第3順位:兄弟姉妹
※配偶者(夫・妻)は常に相続人になります。
このような相続人を「法定相続人」と呼びます。
たとえば、夫が遺言を残さず亡くなった場合、
妻と子どもが二人いれば、不動産などはまず3人の共同名義になります。
でも、話し合い(=遺産分割協議)によって、
「不動産は妻だけの名義にしよう」と決めることがよくあります。
さて、このとき。
「私はもらわないから」と言って相続を辞退する人がたまにいます。
この「もらわない=放棄する」という感覚、実はちょっと注意が必要なんです。
「放棄」には2つの意味がある!
① 日常会話での「放棄」
「私は財産いらないから」と、
遺産分割の話し合いで自分の取り分をゼロにすること。
これは「俗にいう放棄」です。
ただし、これはあくまで“もらわない”だけで、
借金などのマイナスの財産(負債)は引き継いでしまいます。
② 法律での「相続放棄」
一方、法律上の「相続放棄」は全く別物。
相続そのものをしません、という正式な手続きで、
家庭裁判所に申し立てて認められると、
「最初から相続人でなかった」ことになるという強い効力があります。
こちらは、主に借金などのマイナス財産を引き継がないために行うものです。
実際にあった!「放棄」の勘違いで大ピンチ
ある日、私の事務所に田中一郎さん(仮名)がいらっしゃいました。
「父が亡くなったので、実家の名義を母に変えたい」とのご相談です。
話を聞いて、私は「遺産分割協議書を作りましょう」とご提案しました。
ところが――
一郎さんが「これ、相続放棄の証明書です」と差し出してきたんです!
そう、一郎さんは
「自分は財産をもらわない=相続放棄」と思って、
家庭裁判所に正式な相続放棄の手続きをしてしまっていたのです…。
放棄の結果、どうなった?
一郎さんが放棄したことで、
本来は妻と子だけで済んだ相続が、
夫の兄弟やその子どもたち(しかも行方不明の方まで)に相続権が移ってしまいました。
つまり、実家の名義をお母様に変えるには、
まったく面識のない親戚全員の協力が必要になってしまったのです。
このままでは、相続登記が非常に難しい状況に…。
奇跡的に取り消し成功!
一度受理された相続放棄は、原則として取り消すことができません。
でも、一郎さんはあきらめず、裁判所に事情を丁寧に説明しました。
「高齢の母に負担をかけたくなかった」
「相続そのものを放棄したつもりはなかった」
こうした真摯な思いが伝わったのか、
家庭裁判所は特別に相続放棄の取り消しを認めてくれました。
そして無事、実家の名義をお母様に変更することができたのです。
今日のポイント:早めの相談が安心への第一歩
今回のケースは、たまたまうまくいった“奇跡的な例”です。
通常、相続放棄は取り消すことが非常に難しく、
一度の判断ミスが、大きな問題を引き起こしてしまいます。
「もらわないつもりだっただけ」
「放棄=相続放棄だと思った」
そんな“うっかり”を防ぐためにも、
専門家への相談は早めに、が鉄則です。
相続にまつわる不安や疑問があれば、
どうぞお気軽にご相談くださいね。
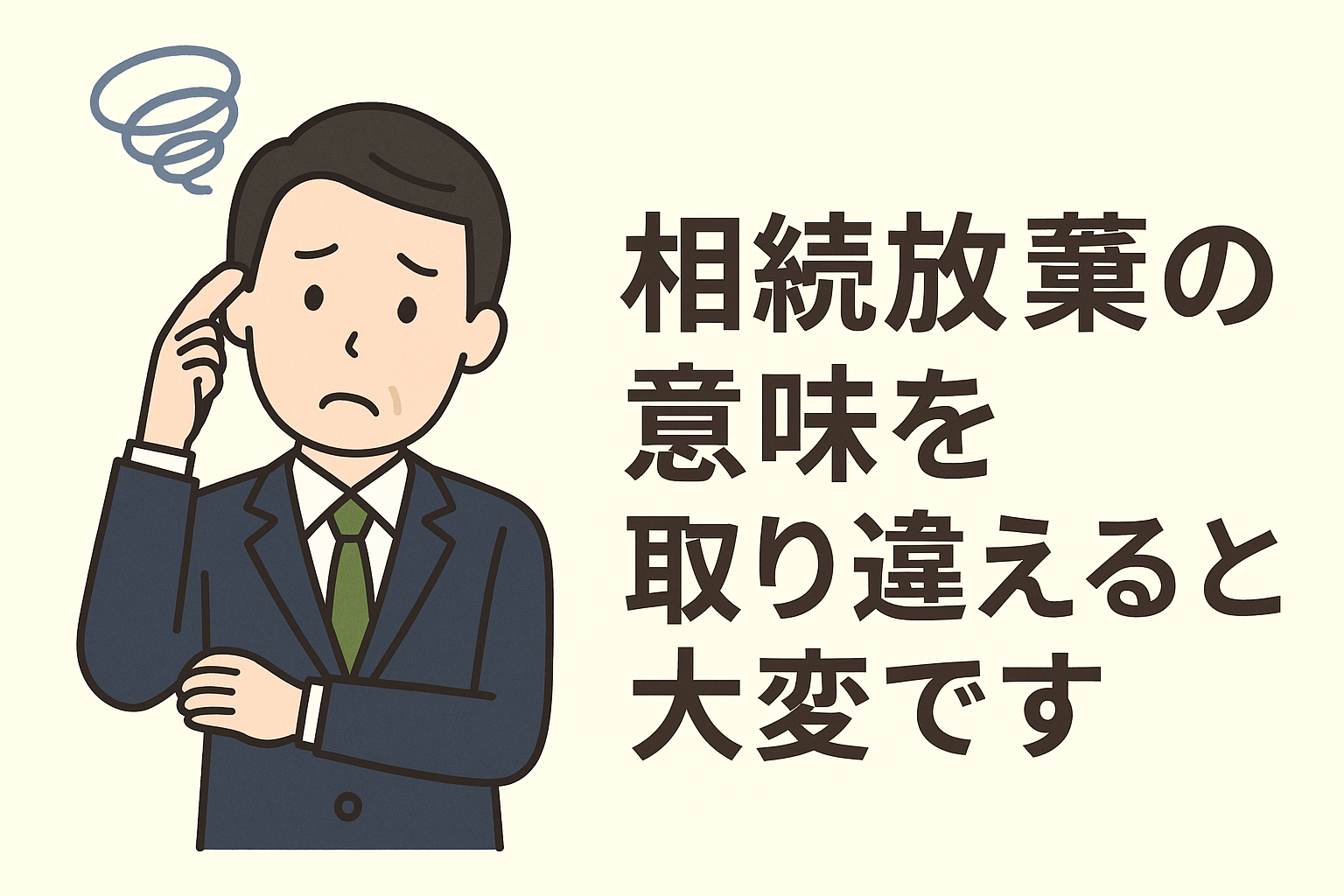
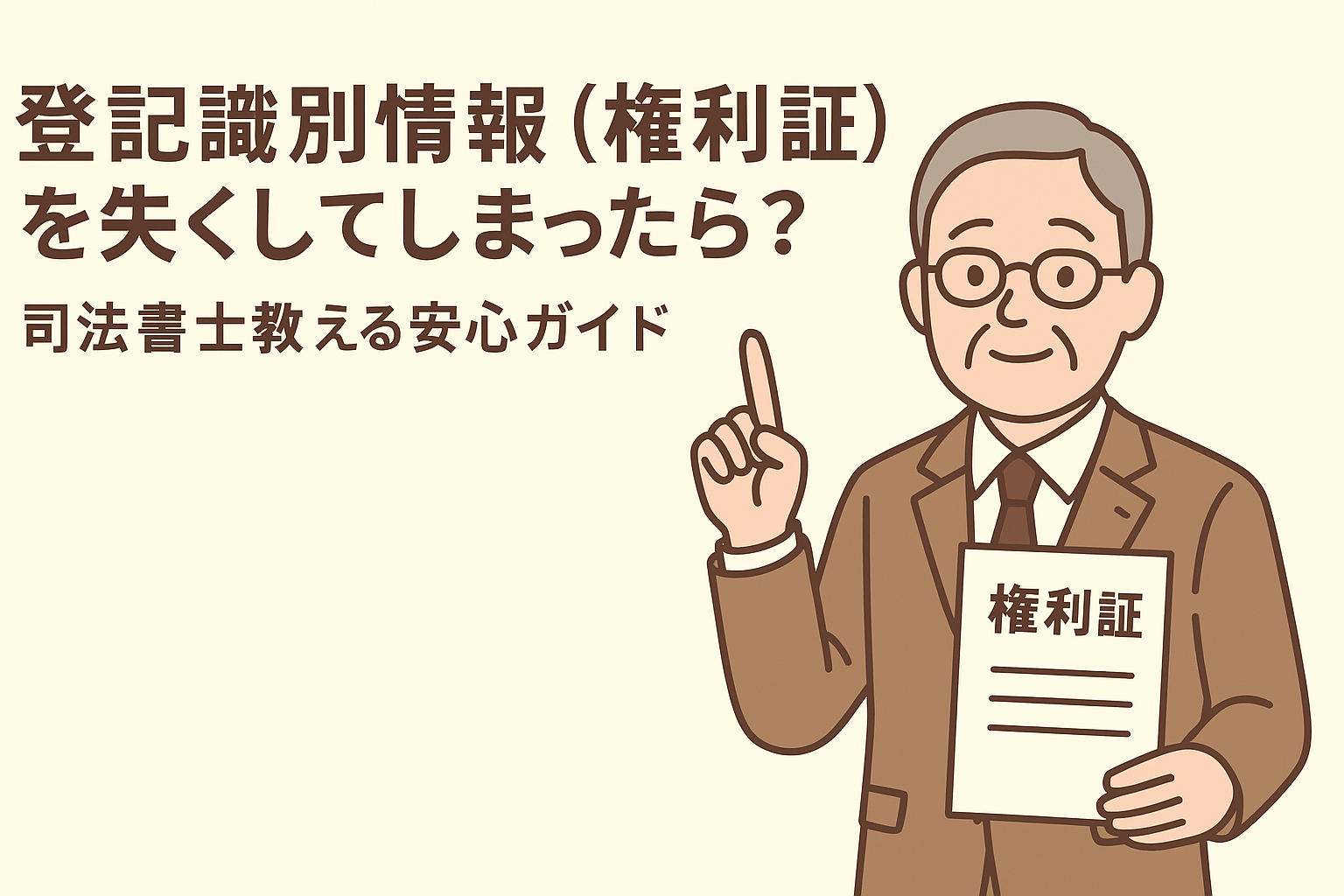
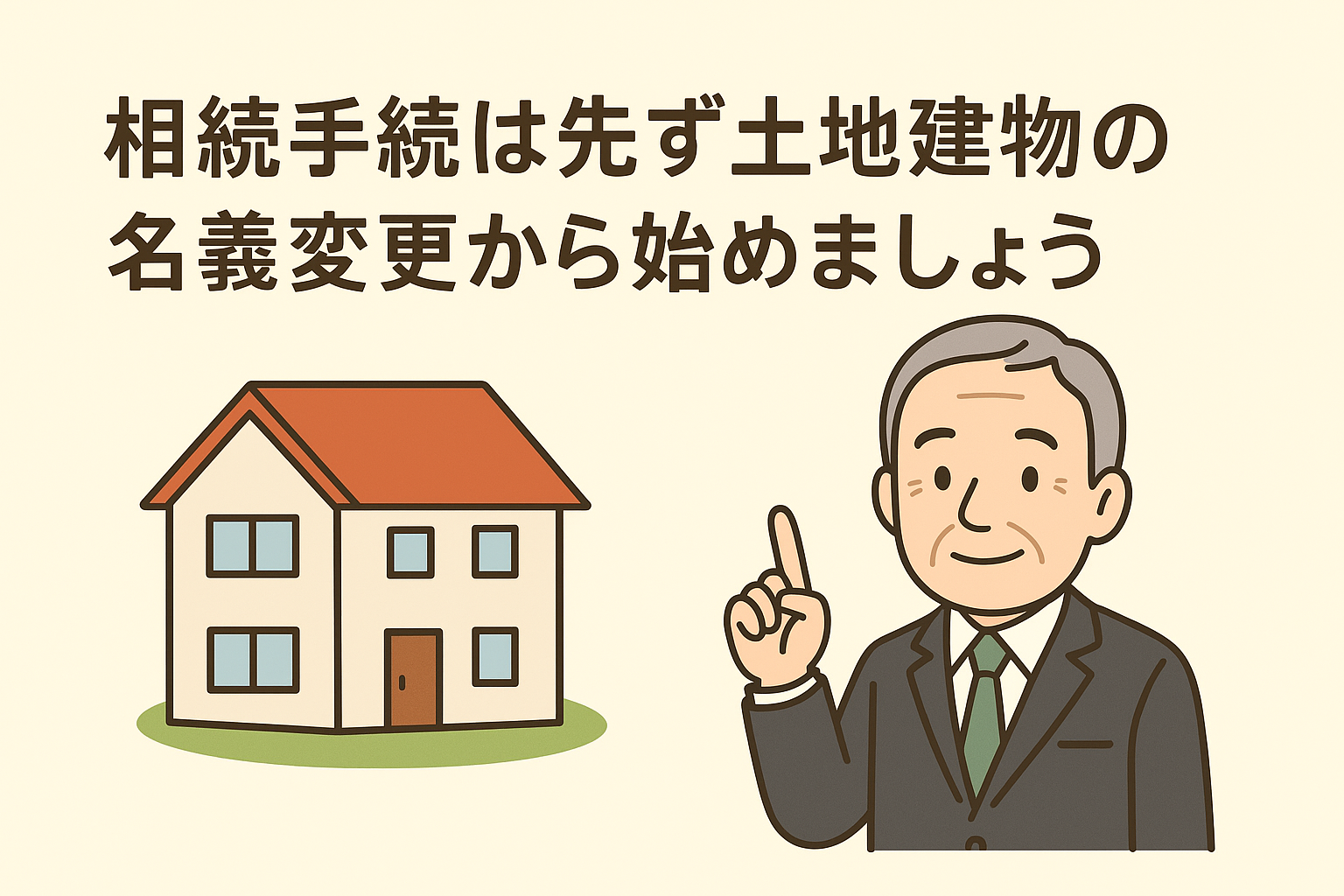
コメント