「お母さん、これ以上引き出せないって…どういうこと?」
私は銀行のATMの前で呆然と立ち尽くす母の横で、画面に表示された「お取引できません」というメッセージを見つめていました。父が亡くなってからまだ3日目。葬儀の費用を支払うために父名義の口座からお金を引き出そうとしたところでした。
想定外の「口座凍結」の現実
父は家計の大黒柱でした。毎月25日には彼の給料が振り込まれる口座から、住宅ローン、光熱費、食費など、家族の生活費のほとんどが自動引き落としされていました。母も働いていましたが、父の収入がメインだったのです。
しかし、父が急性心筋梗塞で突然亡くなった翌日、母が父のキャッシュカードで少額のお金を引き出せただけで、次の日には完全に利用できなくなりました。馴染みにしている銀行の受付の女性に父の死を伝えてしまったのです。
「でも、お父さんのお金なんだから、私たち家族が使えるのは当然じゃない?」
私はそう思いましたが、現実はそう単純ではありませんでした。銀行員から丁寧ながらも冷たい説明を受けました。
「お客様の口座は、名義人様がお亡くなりになられたため、法定相続人の方々の権利を保護する目的で一時的に取引を停止させていただいております」
つまり、父の死亡を知った銀行は、父名義の預貯金に関わる一切の取引を禁止したのです。これが「口座凍結」と呼ばれる対応だと、後で詳しく調べて知りました。
法律上の「預貯金債権」という考え方
混乱の中で私は知り合いの司法書士に電話で質問をしてみました。
「預貯金というのは、法律的には預金者が銀行に対して持つ『金銭の支払いを請求する権利』なのです。これを『預貯金債権』と呼びます。」
そして相続の場合、この権利は相続人それぞれに定められた割合で別々に帰属するとのこと。母と私(一人っ子)の場合、民法の規定により、それぞれが2分の1ずつの権利を持つことになります。本来なら、母は自分の権利である2分の1分を単独で請求できるはずなのです。
「それなのに、なぜ銀行は引き出しを拒否するのですか?」と私は疑問に思いました。
司法書士は少し困ったような表情を浮かべながら答えました。「それは銀行の保身だと思います。他の相続人から『勝手に払い出した』とクレームをつけられるリスクを避けているだけなんです。法律で絶対に禁止されているわけじゃない」
葬儀費用の捻出に奔走した日々
「どうしよう…葬儀費用がまだ全部払えていないのに」
母の声には焦りが混じっていました。父の死は突然だったため、十分な葬儀の準備金もありませんでした。幸い、母名義の口座に少額の貯金があったため、何とか葬儀は執り行えましたが、葬儀社への残金支払いや、これからの生活費を考えると不安でいっぱいでした。
銀行で相談すると、口座解約には以下のような書類が必要だと説明されました:
- 被相続人(父)の戸籍謄本(死亡記載のあるものから遡って出生にいたるまでのもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員の実印を押した同意書
- 相続人全員の本人確認書類
さらに、これらの書類を揃えても手続きには数週間かかるとのこと。
「でも、私たちは明日から食べるご飯にも困るかもしれないのに…」
私たちは親戚や友人からお金を借りて、当面の生活費を工面することになりました。
知っておくべき緊急時の対応策
途方に暮れていた時、母の友人が「遺産分割前でも預金の一部を引き出せる制度があるよ」と教えてくれました。調べてみると、2019年の民法改正で、相続人は遺産分割前でも一つの金融機関につき最大150万円まで仮払いを受けられるようになっていることを知りました。
早速銀行に行き、この制度について尋ねると、必要書類として:
- 相続人であることを証明する戸籍謄本
- 預金額の明細と必要額を記載した申請書
- 相続人の本人確認書類
が必要とのこと。手続きには1〜3週間かかるとされ、すぐにお金が必要な私たちには依然として長く感じられました。
口座凍結前の引き出しという選択肢の危険性
父の兄である叔父から「実は多くの人が口座凍結される前に引き出しておくものだよ」と言われました。実際、父が入院中に「もしものとき」に備えて引き出しておくという選択肢もあったのかもしれません。
しかし、さきの司法書士によると、そういった行為には注意が必要とのことでした。
「相続人が相続財産の全部または一部を処分すると、法定単純承認という状態になる可能性があります。つまり、亡くなった人の借金も全て引き継ぐことになってしまう」
幸いにも父には目立った借金はありませんでしたが、もし隠れた債務があった場合は大変なことになっていたかもしれません。相続放棄や限定承認(プラスの財産の範囲内でのみ債務を引き継ぐ方法)の選択肢を失う可能性があったのです。
3ヶ月後 – やっと解決した口座問題
必要な書類をすべて揃え、手続きを進めて約3ヶ月後、ようやく父の口座の解約手続きが完了しました。その間、私たちは様々な困難に直面しました:
- 自動引き落としされていた公共料金の滞納通知
- クレジットカードの支払い遅延による手数料
- 住宅ローンの一時的な支払い停止手続き
最終的には父の預金を相続できましたが、口座凍結から解除までの間の金銭的・精神的ストレスは計り知れないものでした。
この経験から学んだ教訓
この苦い経験から、私たち家族は財産管理について真剣に考えるようになりました。
- 複数口座での管理の重要性:母は自分名義の口座を増やし、家計の管理方法を見直しました。一つの口座に頼らない体制作りが重要だと実感しました。
- 家族間での情報共有:母は私に全ての口座情報と資産状況を共有し、いざというときに慌てないようにしました。
- 緊急用現金の準備:家の中に適切な額の現金を保管することにしました。銀行が使えない状況でも最低限の生活ができるようにするためです。
- 金融リテラシーの向上:私自身も将来のために金融や相続に関する知識を積極的に学ぶようになりました。
「銀行は公共機関ではなく、私企業なんだよね。彼らは自分たちを守るために動くんだ」と母が言ったことが印象的でした。確かに、銀行は預金者の便宜よりも、自行のリスク回避を優先します。これは批判するべきことではなく、私たち利用者が知っておくべき現実なのです。
事前に準備できること
今、私はこの体験を多くの人に伝えたいと思っています。家族が亡くなった時、預貯金口座は必ず凍結されます。その事実を知っておくだけで、以下のような対策を立てられるはずです:
- 家族の生活費は複数の口座で管理する: 一人の名義に集中させず、夫婦それぞれの名義で口座を持ち、重要な支払いを分散させておく
- 緊急時のための現金を適切に保管: 1〜2ヶ月分の生活費を現金で安全に保管する方法を考える
- 相続に関する基本的な知識を家族で共有: 「口座凍結」の事実と必要な手続きについて家族会議で話し合う
- 資産管理のプロに相談: 司法書士やファイナンシャルプランナーに相談し、家族の状況に合わせた対策を立てる
- 相続手続きに必要な書類を事前に確認: 各金融機関によって必要書類が異なるため、主要取引銀行の要件を調べておく
悲しみの中での実務的な対応
父の死から半年が経ちました。今でも父のことを思い出すと胸が痛みますが、あの時の金銭的な不安と混乱は、悲しみをさらに深くしたように感じています。
悲しみに暮れる時に金銭的な不安が重なるのは本当に辛いものです。大切な人との別れを悼む時間が、手続きに追われる日々にならないよう、今からできる準備を始めることをお勧めします。
私たちの経験が、そして何より、突然の別れが訪れたとき、愛する人を失った悲しみに十分に向き合える環境を整えておくことが、本当の意味での「終活」なのかもしれません。
この記事は、実際の相談者の事例をもとにその方の承諾を得て司法書士の小椋が執筆したものです。同じような状況にある方の参考になれば幸いです。

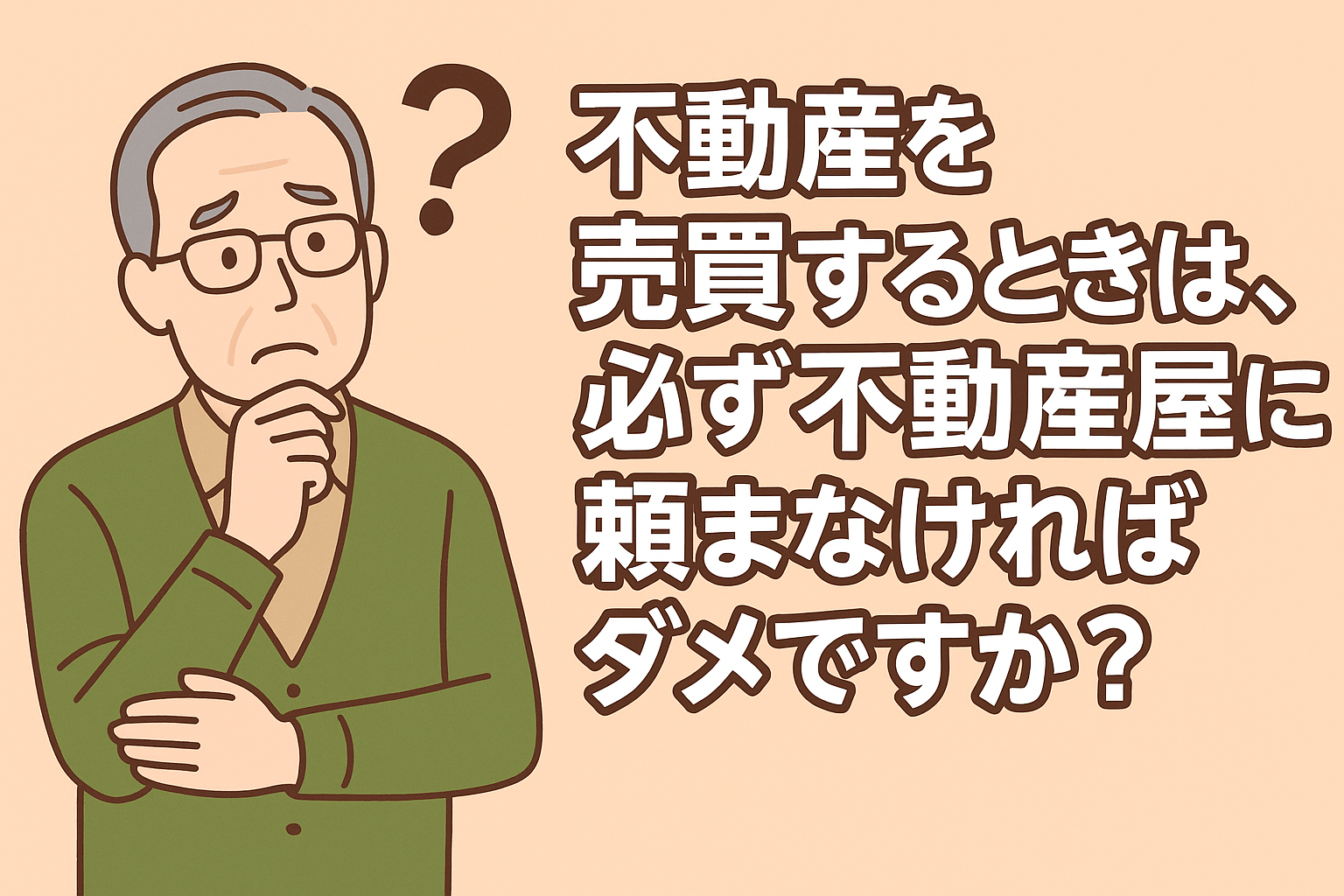
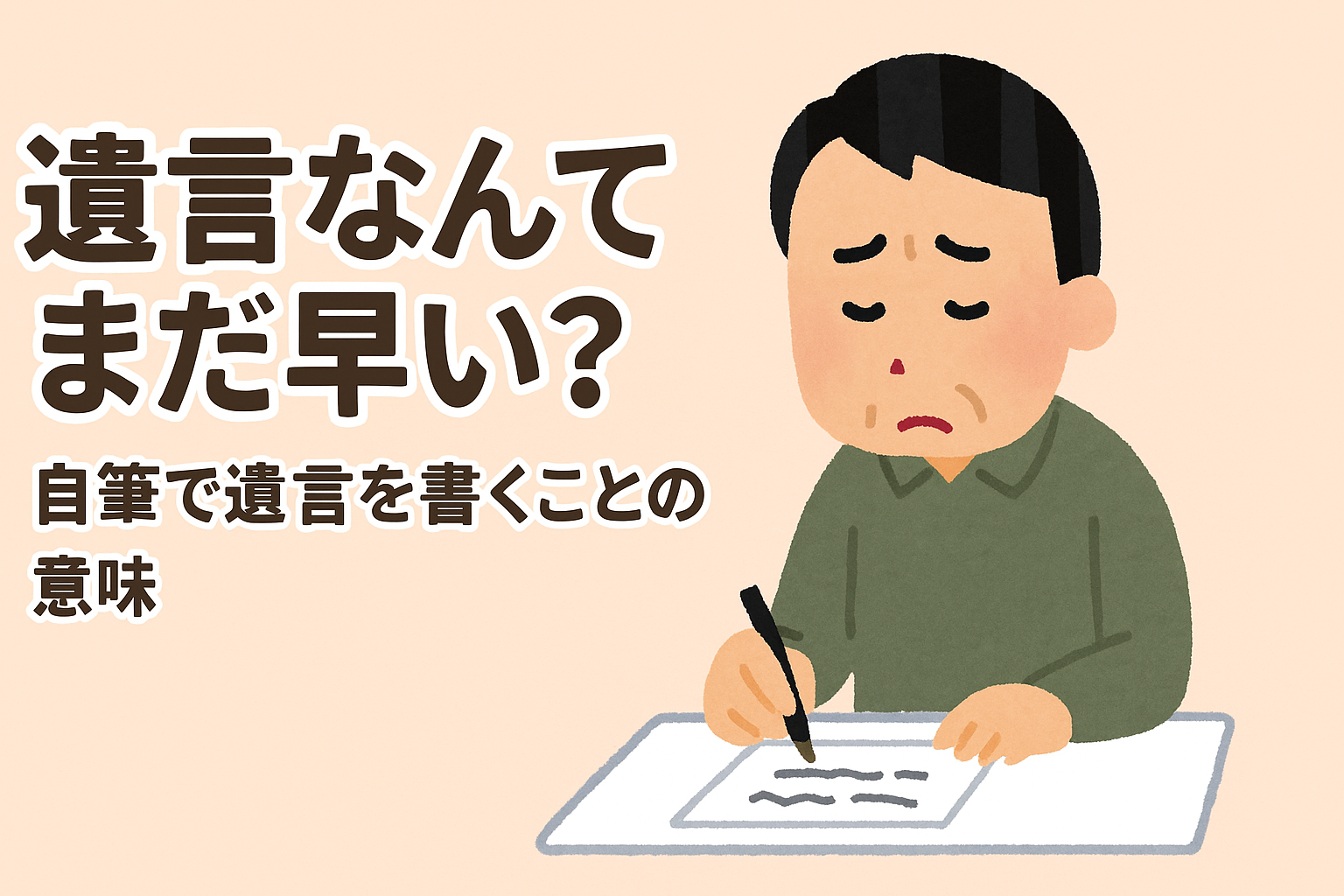
コメント