2025年4月、日本のすべての企業に「65歳までの雇用確保」が義務化されます。これは、深刻化する少子高齢化による人手不足に対応し、シニア世代が安心して働ける環境を整えるための制度です。
しかし注意したいのは、「定年を65歳に引き上げなければならない」という制度ではないこと。実は企業ごとに柔軟な対応が認められているのです。
この記事では、「65歳までの雇用確保」の制度内容と、企業がとるべき対応策、さらに導入によるメリットと課題についてわかりやすく解説します。
「65歳までの雇用確保」は定年延長じゃない?企業が選べる3つの方法
新制度では、希望する従業員が65歳まで働ける環境を整えることが企業に求められます。ただし、必ずしも定年を65歳にする必要はありません。企業は次の3つの方法から選べます。
① 定年延長(例:60歳→65歳)
最もシンプルな方法です。従業員はこれまで通りの条件で65歳まで働けます。
メリット:モチベーションの維持、離職防止
デメリット:人件費増、若手の昇進機会の減少
② 継続雇用制度(再雇用・雇用延長)
60歳で一度定年を迎え、その後も希望者には65歳までの雇用を保証する方法です。
- 雇用延長:同じ条件で働き続ける
- 再雇用:契約社員など別形態で再スタート
メリット:柔軟な雇用条件の設定が可能
デメリット:給与ダウンでモチベーションが低下する可能性あり
③ 定年制の廃止
定年そのものをなくして、本人の希望があればいつまでも働ける制度です。
メリット:ベテラン人材の長期活用
デメリット:若手の成長機会が減るため、人事制度の再設計が必要
企業が今すぐやるべき4つの準備
制度の開始は目前。企業が円滑に対応するために、今から取り組むべき4つの対応策をご紹介します。
1. 就業規則の見直し
継続雇用や定年延長をするには、まず就業規則の変更が必要です。
変更内容は労働基準監督署への届け出も必要なので、早めの準備がカギです。
2. 賃金制度の再設計
60歳以降の給与をどうするかは大きな課題。
- 同じ給与で働き続けるか
- 再雇用時に調整するか
評価制度の見直しも含め、「納得できる仕組み」が重要です。
3. シニアが働きやすい職場づくり
柔軟な勤務時間や業務内容の調整、若手の指導役など、シニアならではの役割を設けると効果的。
シニアの経験を活かしながら、全体の生産性アップにもつながります。
4. 継続雇用の意思確認
定年が近い社員には、「65歳まで働きたいか?」を事前に確認しておきましょう。
トラブル防止のため、書面での確認がベストです。
これからの時代に合ったシニア雇用のカタチを考えることが大事
「65歳までの雇用確保」は、ただ義務だから対応する…という話ではありません。
これは、日本の未来を支えるシニア世代の活躍をどう後押しするかという、重要なテーマでもあります。
高齢者がやりがいをもって働ける職場を整えることは、企業にとっても大きなメリット。
制度をうまく活用し、持続可能な組織づくりを目指していきましょう!
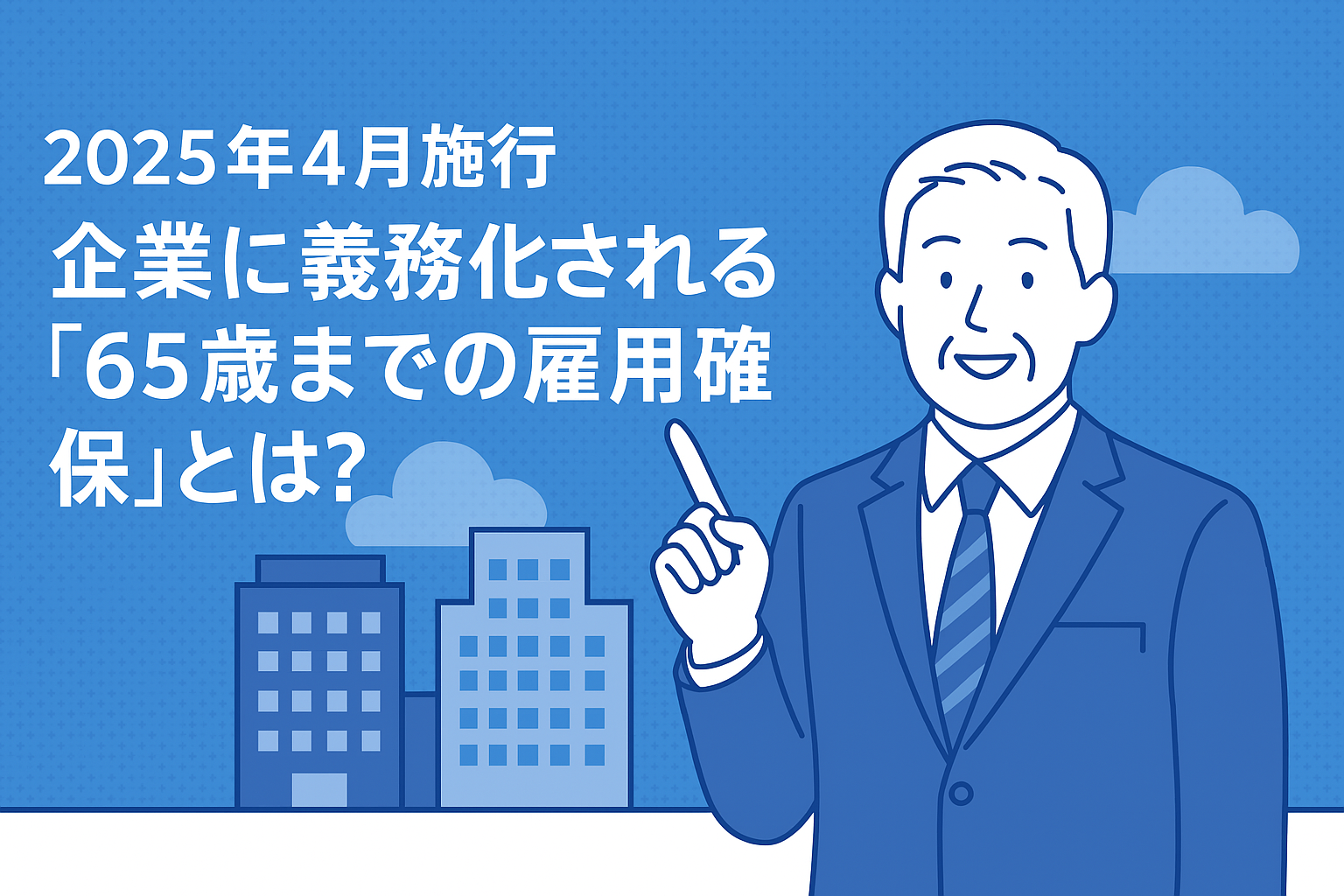
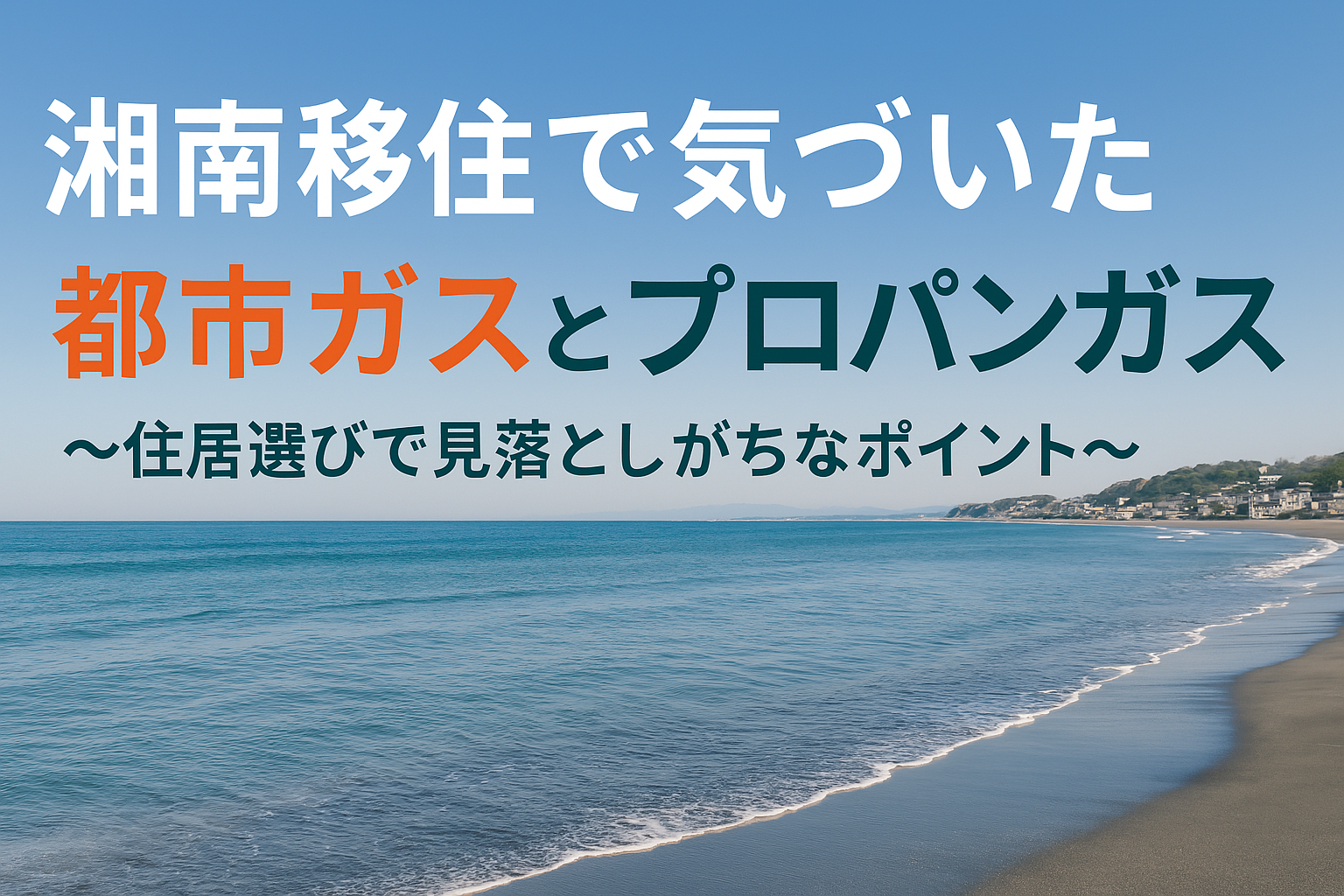
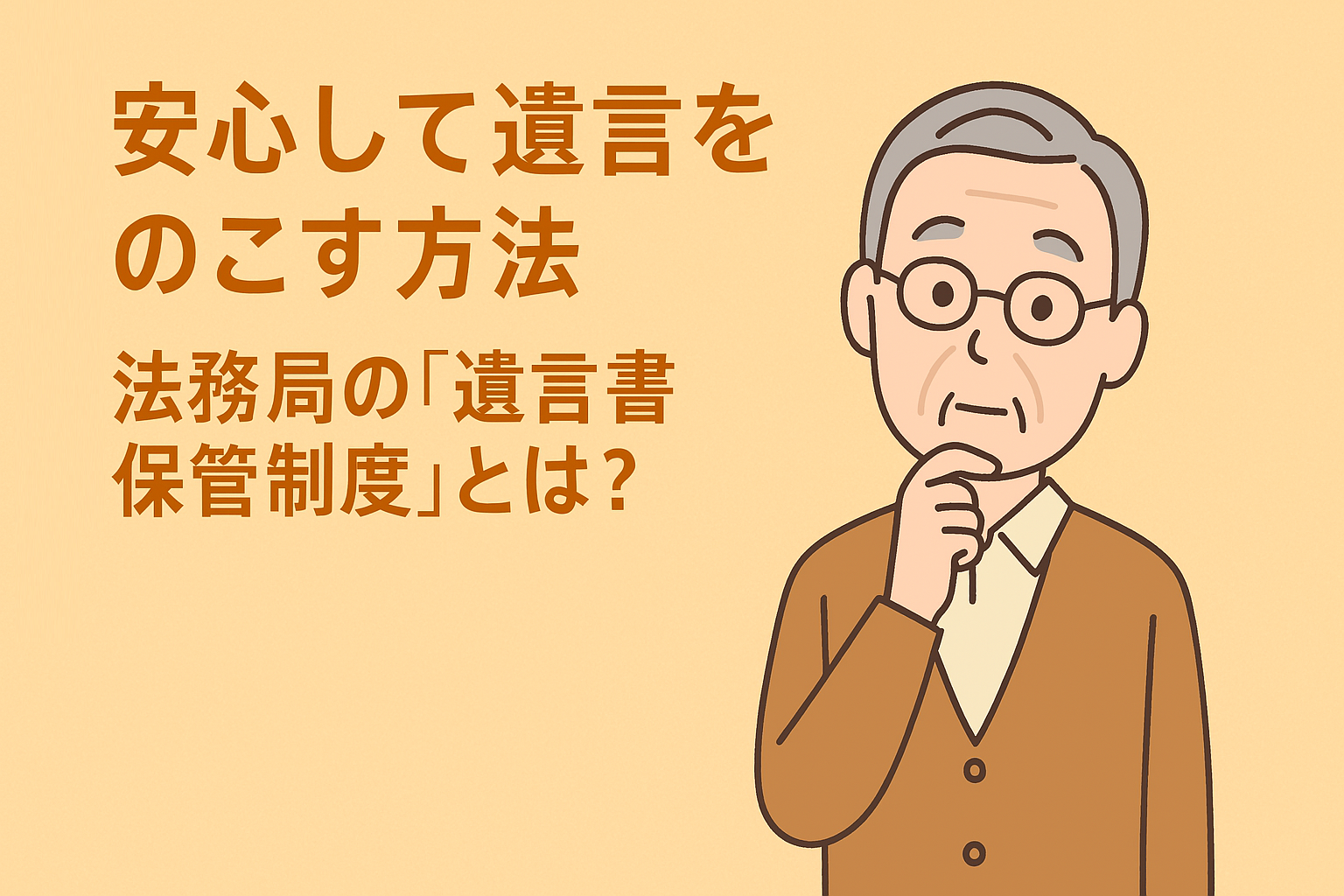
コメント