序章 忘れられがちな不動産登記の重要性
「登記?そんなもの、普段気にしたことないなぁ…」
これが多くの方の本音ではないでしょうか。確かに、自分の土地や建物の登記について、日常的に意識している人は決して多くありません。
しかし、遺言書を作成する時や、遺産分割の協議をする時に、登記の対象となる不動産を見落としてしまうと、後々想像以上に面倒なことになってしまうのです。
今日は、実際に私の事務所に相談に来られた久保田健太さん(66歳・仮名)の体験談を通じて、多くの方が見落としがちな「私道」の相続問題について、ご説明させていただきます。
第1章:久保田さんの家族の物語
38年間の幸せな共同生活
久保田健太さんは、38年前に結婚と同時に、妻光代さんの母親、つまり義母の川中つや子さん名義の土地の上に自宅を建てました。そこで夫婦と娘二人、そして義母の5人で仲良く暮らしてきました。
時が過ぎ、次女は結婚して家を出ましたが、家族の絆は深く、久保田さんは義母をまるで実の母親のように大切にしてきました。
突然の別れ
ところが、7年前に不幸が襲いました。奥さんの光代さんが病気で亡くなってしまったのです。
久保田さんは深い悲しみに包まれましたが、奥さん亡き後も義母である川中つや子さんの身の回りの世話を献身的に続けました。まるで実の息子のように…
義母の思いやり
川中つや子さんには、娘が二人いました。久保田さんの奥様だった光代さんと、その妹の坂本佳代さんです。川中つや子さんの夫は既に他界していました。
つまり、光代さん亡き後は、久保田さんの娘さん二人と坂本佳代さんが相続人になります。
このことを知った川中つや子さんは、ある決断をしました。
「健太さんに自宅の土地を遺贈しよう」
実は、この土地は川中つや子さんの名義になっていましたが、久保田さんが購入代金のおよそ半分を出していました。また、実の息子のように面倒を見てくれる久保田さんへの感謝の気持ちを形にして、将来のトラブルを避けることが目的でした。
完璧に思えた遺言書
川中つや子さんは、公証役場に権利証などを持参し、遺言を作りました。坂本佳代さんには金銭を相続させ、その代わりに、久保田健太さんには自宅の敷地になっている土地を遺贈するという内容です。
遺言書には、遺贈の対象として2筆の土地の記載がありました。公正証書遺言でしたので、法的にも完璧に思えました。
第2章:予想外の落とし穴
司法書士事務所での相談
今般、川中つや子さんが高齢のため亡くなり、その遺言書を携えて、久保田健太さんは私の事務所に来られました。
久保田さんは安堵の表情を浮かべながら言いました。
「先生、義母が公正証書遺言を残してくれたので、手続きは簡単ですよね?」
司法書士の勧め
私は久保田さんに対し、移転登記の必要書類である評価証明書を取得する際に、念のため、私道の有無を役所の窓口で確認することをお勧めしました。
「えっ?私道ですか?そんなものあるんでしょうか…」
久保田さんは首をかしげましたが、私の勧めに従って市役所の窓口で確認してくれました。
衝撃の発見
すると、案の定、遺言書記載の土地とは別に、近隣の方と共有になっている私道があることが判明したのです。
この私道は、遺言書には記載がありませんでした。当然、遺贈を原因として私道の共有名義を久保田健太さんに移すことはできません。
「そんな…どうしてこんなことに…」
久保田さんは困惑しました。
第3章:私道という見えない土地
私道とは何か
私道とは、個人や私企業が所有している土地である道路のことです。国や市区町村が管理する道路である公道に対する概念です。
私道は、登記上の土地の種類である地目としては、「公衆用道路」であることもあれば、「宅地」とされていることもあります。
なぜ見落としやすいのか
この私道が見落とされる最大の原因は、その多くが固定資産税・都市計画税が非課税とされていることです。
非課税の物件ですから、固定資産税の納付通知書の課税明細書や名寄帳記載事項証明書にはその土地についての記載がありません。
さらに、私道は近隣の土地の所有者と共有になっていることが多く、その権利証を誰が保管しているのかさえわからないことが珍しくありません。
相続時の特別な注意点
自分で購入した土地であれば、メインの土地の他に、公道に出るための通路、私道があることを認識している方が多いといえます。
しかし、自分が住んでいない親の土地建物を相続によって取得するような場合は、私道の存在に気付かない危険性が高くなります。
第4章:問題の解決
新たな手続きの必要性
やむを得ず、この私道については、遺贈による所有権移転登記とは別に、相続を原因として同居している久保田さんの長女にその名義を移すことになりました。
遺産分割には、川中つや子さんの次女坂本佳代さんと、久保田健太さんの二人の娘が、妻光代さんの代襲相続人として協議する必要がありました。
家族の理解と協力
幸い坂本佳代さんを含め、相続人全員が快く了解してくれましたので、無事全ての手続きが完了しました。
「本当に良かったです。皆さんのご理解があって助かりました」
久保田さんは胸をなで下ろしました。
第5章:私道を見つける方法
久保田さんの場合は、私道についてだけ娘さんの名義にするということで、なんとか問題にならなくて済みました。しかし、いつもこううまくいくとは限りません。
それでは、私道のように非課税の土地を見つけるにはどうすればよいのでしょうか。
方法その1:登記事項証明書の共同担保目録を確認する
住宅ローンを利用する場合、銀行等の金融機関は、必ず私道をふくめて全ての土地に抵当権を設定します。ですから、この目録の部分を見れば、私道の有無が判断できるのです。
ただし、この方法は、住宅ローンを利用せず、現金で購入した場合には使えません。
方法その2:市区町村役場の窓口で確認する
実は、この方法が最も有効だったりします。久保田さんの場合もこの方法で私道の存在が確認できました。
具体的には、評価証明書を発行する窓口で、次のように告げるだけです。
「もしかすると、同じ名義人の非課税の土地もあるかもしれません。あったときは、その非課税証明書も発行してください。」
エピローグ:専門家のアドバイス
せっかく公正証書で遺言を残したり、相続人全員で遺産分割協議書が無事作成できたとしても、対象不動産の一部を漏らしてしまうと後々トラブルにならないとは限りません。
まずは権利証のチェックから
ご自分の土地建物に関して、まずは権利証をチェックすることから始めて、その内容を再確認してはいかがでしょうか。
法務局に出向いて登記事項証明書を取ることだけでも意味がありますが、できれば専門家である司法書士事務所で相談されると一層安心です。
オンライン対応の司法書士事務所を活用
なお、オンラインに対応している司法書士事務所であれば、わざわざ法務局に行かなくても、登記の内容はその場で確認することが可能です。
久保田さんの事例のように、一見完璧に思える遺言書にも落とし穴があることがあります。相続は人生で何度も経験することではありませんが、だからこそ専門家のサポートが重要なのです。
不動産の相続でお困りの際は、お気軽に当事務所にご相談ください。あなたの大切な財産と家族の絆を守るお手伝いをいたします。
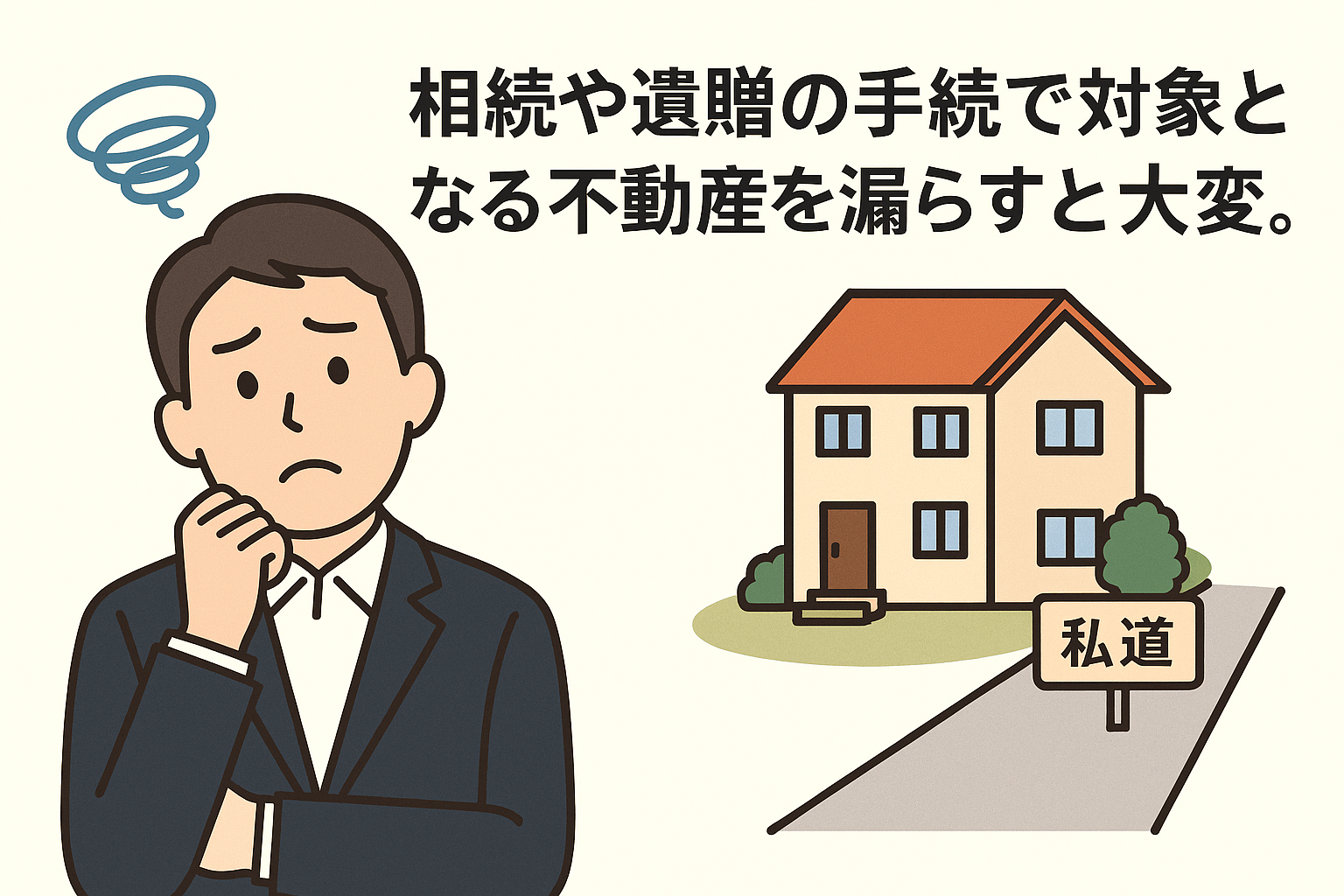
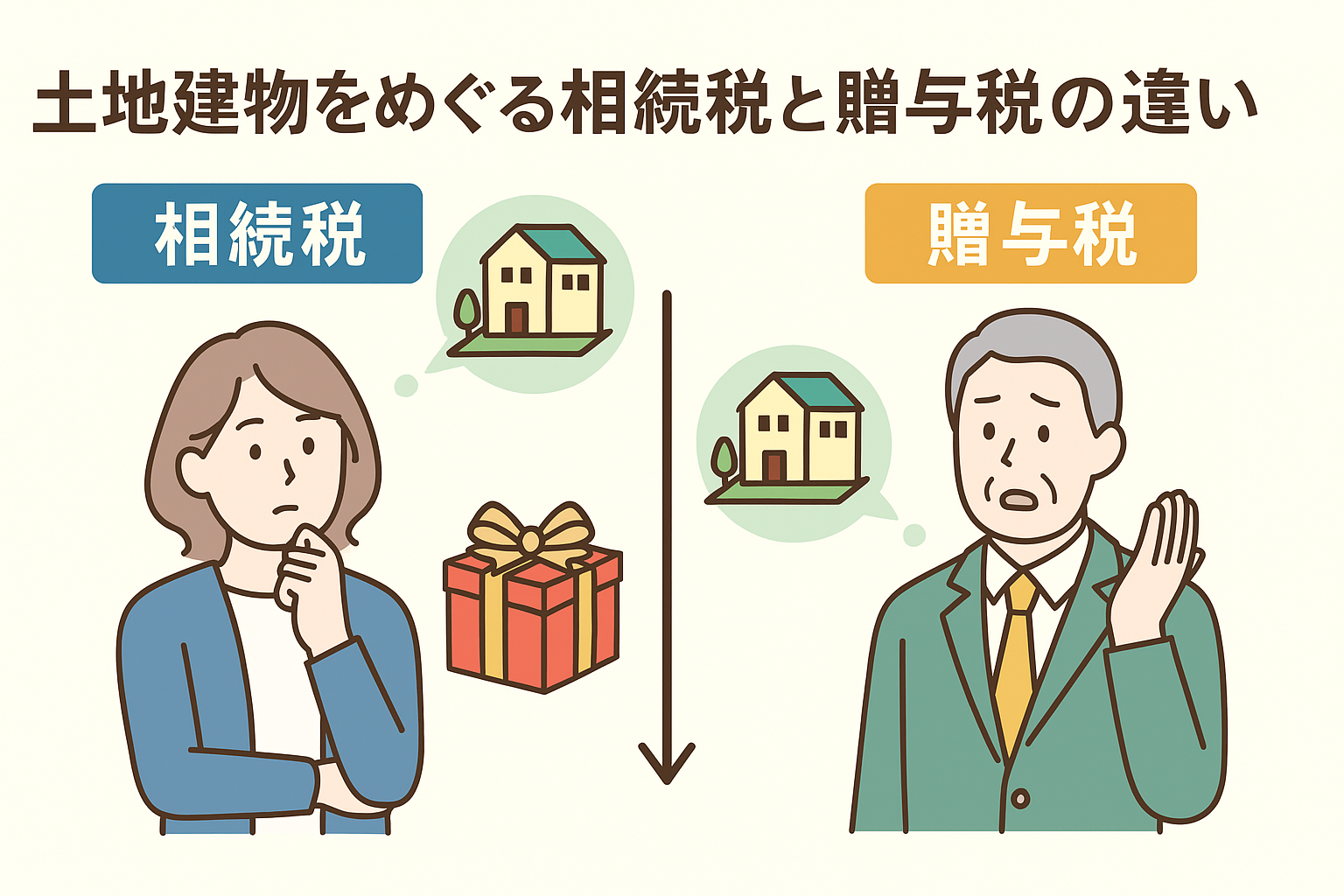

コメント