その電話は、曇り空の火曜日の午後に鳴りました。受話器の向こうから聞こえてきた不安げな声は、私の事務所によくある相談の始まりでした。
「先生、相続のことでご相談があるのですが…長男が行方不明で、どうしたらいいのか分からなくて」
田中さん家族の物語
田中洋子さん(仮名)は、昨年夫を亡くした62歳の女性でした。自宅と敷地は夫の名義のままで、これを自分の名義に変更したいと事務所を訪れました。
「相続人は私と長男、長女の3人なんですが…」と洋子さんは言葉を詰まらせました。「長男が12年以上前から行方不明なんです」
洋子さんの話によると、長男の健太さん(仮名)は複数の金融業者からの借金に困り、徐々に帰宅しない日が増えていきました。ある日、父親から不行状を厳しく叱責された後、家を出たまま連絡が途絶えたのです。
「どこにいるのか、生きているのかさえ分からないんです」と洋子さんは涙ぐみながら話しました。
誤解を解く
「田中さん、ご安心ください。共同相続人の中に行方不明の方がいても、相続登記は可能です」
洋子さんの表情が少し明るくなりました。多くの方が同じ誤解をされていますが、行方不明の相続人がいても登記の方法はあるのです。
健太さんの住民票を調査すると、最後の住所の住民登録は市区町村の職権ですでに消されていました。もはや住所を知る術はありません。こうした状況で選べる方法を洋子さんに説明しました。
三つの選択肢
1. 法定相続分による方法
「まず一つ目の方法は、法定相続分どおりに相続登記を行うことです」
民法で定められた相続分(配偶者と子なら各2分の1ずつ、子が複数いる場合は均等割り)で登記をするなら、行方不明者も相続人の一人として登記が可能です。ただ、健太さんのように住民票が取れない状態では難しい場合もあります。
2. 財産管理人を選任する方法
「二つ目は、家庭裁判所に行方不明者の『財産管理人』を選任してもらう方法です」
財産管理人が行方不明者に代わって遺産分割協議に参加することで、法定相続分と異なる割合での登記も可能になります。ただし、裁判所の許可が必要で、手続きは複雑で費用もかかります。
3. 失踪宣告による方法
「三つ目は、失踪宣告という方法です。行方不明者の生死が7年以上わからない場合、法的に死亡したとみなすことができます」
失踪宣告が認められれば、7年が満了した時点でその行方不明者が死亡したものとして、他の相続人だけで遺産分割協議を成立させることができます。手続きは比較的シンプルで費用も低額です。
「ただ、どこかで生きているかもしれない家族を死亡したとみなすことに抵抗を感じる方も多いです」と付け加えました。
決断の時
洋子さんは悩みました。行方不明になっているのは、やはり自分の息子です。すぐには決められないと言って、長女と相談する時間をとることにしました。
数か月後、洋子さんは長女と共に再訪し、「失踪宣告の方法を選びたい」と話しました。私は、失踪宣告は財産関係を一応決着させるためのもので、もし健太さんがどこかで生存していた場合には取消しができることを説明しました。それを聞いた洋子さんは少し安心した様子でした。
新たな一歩
申立てから半年以上が経過して、失踪宣告が認められました。土地建物の名義変更も、洋子さんと長女の分割協議だけで無事完了しました。
「もし健太が戻ってきたら…」と洋子さんは書類に署名しながら呟きました。
「その時はまた別の手続きができますから、ご心配なく」と私は答えました。彼女の表情に、長年の不安から解放された安堵の色が浮かびました。
司法書士からのアドバイス
共同相続人の中に行方不明の方がいても、相続登記は可能です。状況に応じて最適な方法を選ぶことができます。
- 法定相続分による方法(比較的シンプル)
- 財産管理人を選任する方法(手続きは複雑だが柔軟な分割が可能)
- 失踪宣告による方法(7年以上の行方不明が条件)
どの方法を選ぶにせよ、司法書士のサポートを受けることで、複雑な手続きもスムーズに進めることができます。行方不明の家族がいる相続でお悩みの方は、ぜひ司法書士にご相談ください。家族の事情に応じた最適な解決策を一緒に見つけていきましょう。
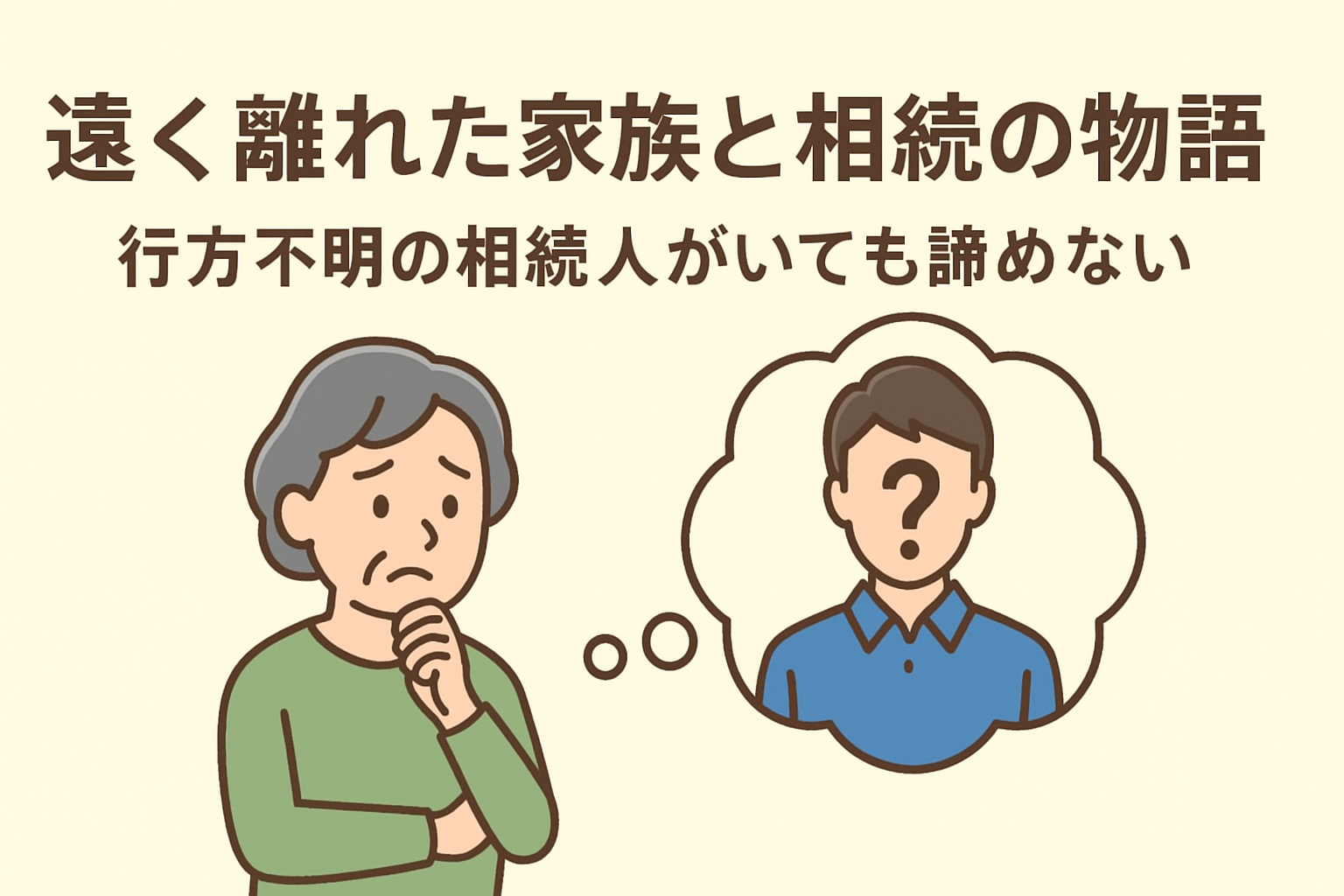

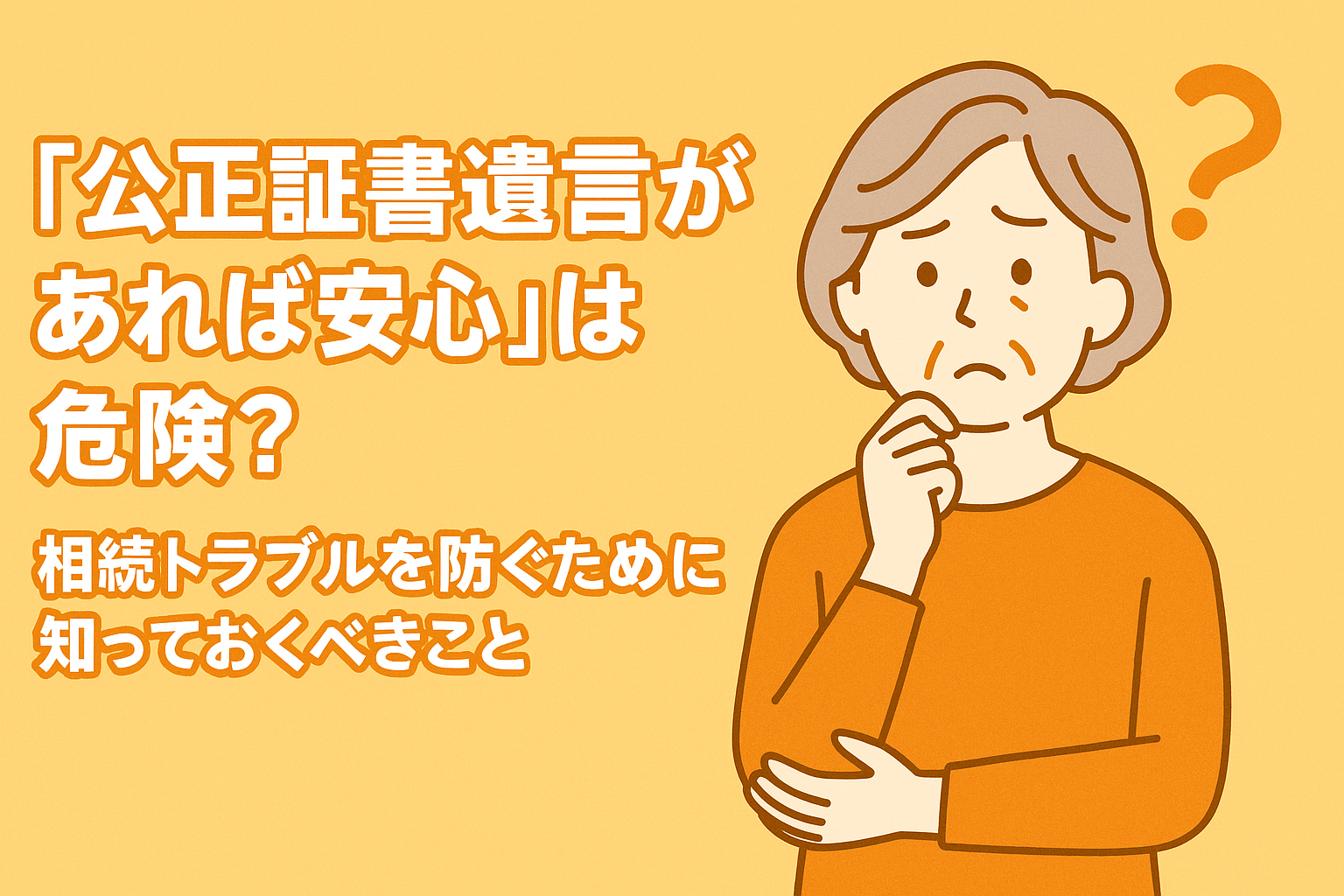
コメント