組織全体の生産性を脅かす「見えない損失」
経営者として、また人事担当者として、一度は直面したことがあるのではないでしょうか。仕事が遅く、ミスが多い。注意をしても改善の兆しが見えない。そんな「ローパフォーマー社員」の存在です。
このような社員を放置することは、単に一人の問題にとどまりません。業務の停滞、他の社員のモチベーション低下、そして最終的には会社全体の競争力削減につながる深刻な経営課題なのです。
実際の相談事例:社員思いの経営者の悩み
先日、ある顧問先の社長からこのような相談をお受けしました。創業8年で3名から8名まで成長した会社の代表です。社員思いで定着率も高い、まさに理想的な経営者の方でした。
「何度注意しても同じミスを繰り返す社員がいます。これまで改善を期待して恩情で昇給させてきましたが、もう限界です。減給を検討していますが、法的に問題ないでしょうか?」
この相談の背景には、3~4年にわたる地道な改善努力がありました。再三の注意、方針説明での明確な基準提示、それでも改善されない現実。経営者の苦悩が痛いほど伝わってきました。
賃金カットという「安易な解決策」の落とし穴
多くの経営者が考える減給という手段ですが、実は法的にはかなり困難な道のりです。
労働基準法上、会社が一方的にできる賃金カットは「制裁」としてのもののみ。しかも以下の厳格な制限があります:
- 1回の減給額:平均賃金の1日分の半額以下
- 総額:1か月の賃金総額の10分の1以下
- 期間:1か月限り
- 前提:就業規則への明記が必要
つまり、継続的な賃金引き下げは従業員の同意なしには原則不可能なのです。
賃金カットを検討する際の6つの留意点
それでも賃金調整が必要な場合は、以下の点を慎重に検討する必要があります:
- 月例賃金より賞与の調整を優先する
- 就業規則に降格・降給の根拠を明記する
- 客観的で具体的な人事考課制度を整備する
- 役職変更・職務変更を伴う形にする
- 十分な説明と協議を尽くす
- 経過措置を設け、段階的な調整とする
本質的な解決に向けて:排除ではなく適材適所を
ローパフォーマー社員への対応に特効薬はありません。しかし、だからといって放置することは許されません。
重要なのは、その社員が本当に「能力がない」のか、それとも「適性に合わない職務についている」のかを見極めることです。転職支援を通じて、その人の適性が活かせる環境を見つけることも一つの解決策となり得ます。
また、一度採用した責任は会社にもあります。最終的に退職という結果になるとしても、可能な限り本人が納得し、前向きに会社を離れられるよう働きかけることが、人としての誠実さであり、企業としての責任でもあるのです。
早期対応が組織の健全性を保つ
ローパフォーマー社員の問題は、時間が経つほど解決が困難になります。法的リスクを避けながら、組織全体の生産性と士気を維持するためには、早期の適切な対応が不可欠です。
人事制度の整備、客観的な評価基準の設定、そして何より、一人ひとりの社員と真摯に向き合う姿勢。これらが、健全な組織運営の基盤となるのです。
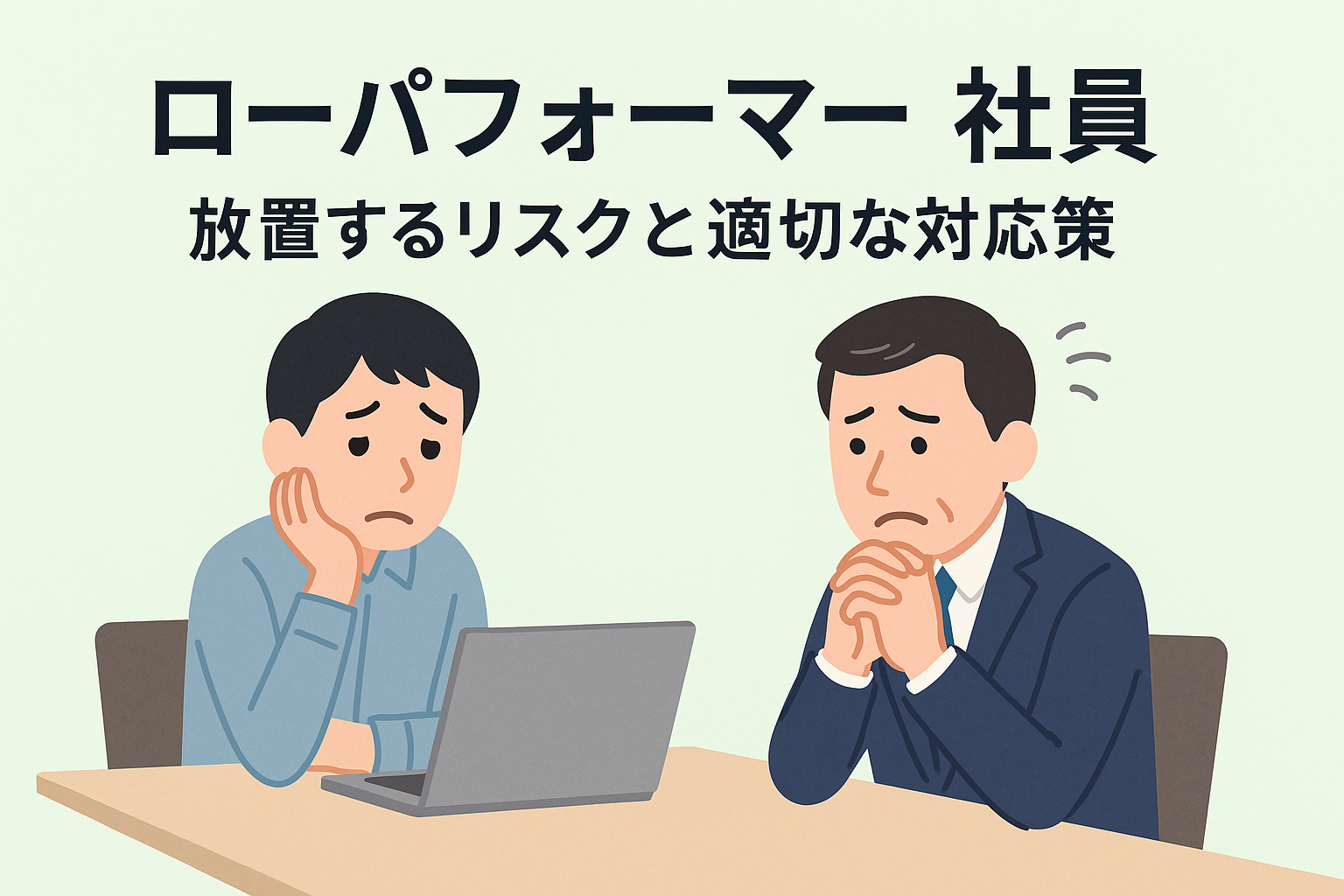
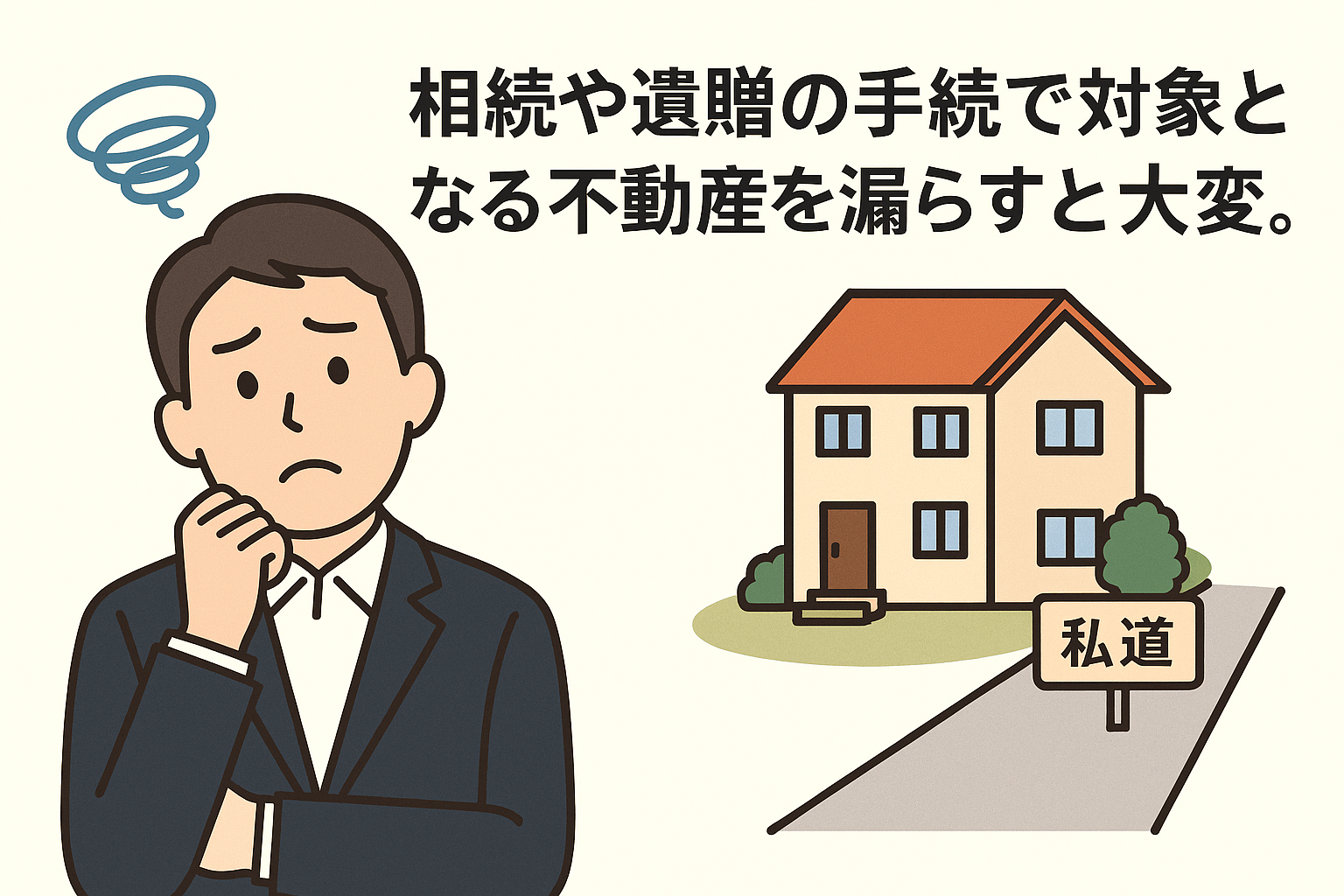

コメント