不動産を共有する事情は様々なものがあります。
・共働きの夫婦が住宅を購入する際、
夫婦ともに住宅ローン控除を受けるために共有にする。
・二世帯住宅を建てて親子で共有にする。
最近では
・同居する未婚の兄弟姉妹を加えた
2.5世帯住宅などという共有の住宅まで登場しています。
これらの多くは、税金の面で有利だとか、
夫婦や親子・同居する兄妹と所得を合算して、
より多額の住宅ローンが組めるといった
購入時の資金面でのメリットがあるのは事実です。
しかし、
共有にすることのリスクを十分に理解し、
準備をしておかないと後悔することになるかも知れません。
そこで今日のテーマ
──────────────────────────────────
不動産を共有するリスク
──────────────────────────────────
そもそも「共有」とは、広い意味では共同所有のことです。
不動産の共有とは、
一筆の土地や一棟の建物を数人が共同して所有している状態です。
これに対して、
1人の所有者が所有している形態を「単有」ということがあります。
各共有者が持っている権利を持分とか持分権といいます。
持分権は、他の共有者による制限を受けているものの、
ひとつの権利として、所有権と同じ性質を持つとされています。
したがって、法律でも、
各共有者は、
共有物の全部について、その持分の割合に応じた使用をすることができ、
また、収益・処分をすることができるとされています。
問題なのは、
持分権が独立の権利として認められている反面、
共有物全体については、共有者全員の同意がなければ、
これに変更を加えることができないとされている点です。
ここにいう「変更」とは、共有物の性質や形状を変更することだけでなく、
処分することも含まれるというのが通説であり、裁判所の見解でもあります。
例えば、
共有の山林を伐採したり、
共有の不動産全体に抵当権を設定したり、
共有物を売却するためには、共有者全員の同意が必要になります。
つまり、1人で所有している場合とは異なり、
権利関係が複雑になり、共有者はそれぞれ他の共有者の意向を無視して、
自由にその共有物を処分したり、変更したりすることが出来なくなるのです。
このことが、不動産を共有することの最大のリスクだといえます。
ところが、このリスクを十分認識している人は必ずしも多くありません。
不動産業者は、より高額の物件を販売することしか関心がないので、
当然と言えば当然です。
夫婦でも、親子でも、あるいは兄弟姉妹でも、
所得を合算してより多くの資金を捻出する方法しかアドバイスしないでしょう。
金融機関も、ローンの回収が確かであれば、
共有にすることに難色を示すはずがありません。
その結果、特に親族同士の共有物件が多く存在することになります。
勿論、
親族同士で資金を出し合って不動産を購入することが
問題だということではありません。
皆で住む住宅なのだから、当然応分の費用を負担しよう、
そうすれば、1人で購入するよりも、より広い土地、より良い住宅が手に入る。
多くの人がそう考えるのは当然だと思います。
確かに、購入して間もない頃は、トラブルが起きることも少ないでしょう。
しかし、月日が経てば、諸々の事情が変化することは避けられません。
親族間の人間関係とて、いつまでも円満にいられるという保証はありません。
共有の不動産を巡って実際に起こったトラブルの実例を紹介します。
事例1)抵当権抹消のご依頼を頂いたAさんの場合。
約10年前、一人娘が結婚した際に、娘婿と資金を出し合って、
同居するマンションを購入しました。
Aさんと娘婿がそれぞれ2分の1の割合で共有することになりました。
今般、住宅ローンを繰り上げ返済したとのことで、
抵当権抹消のご依頼に来られました。
事情をお聞きすると、娘婿は、結婚後すぐに暴力団関係者と判り、離婚。
マンションを出たまま、現在は行方知らずとのこと。
ローンも全てAさんだけで返済しました。
抵当権抹消は、共有物全体の保存行為ということで、
共有者の一人からでも申請することができます。
しかし、今後、このマンションを売却することは、
相当難しいとお伝えする他ありませんでした。
この例のように、
離婚の際に、住宅の共有状態をそのままにしたために、
後々、売ることが著しく困難になっている住宅は、決して珍しくありません。
事例2)古いマンションの相続登記のご依頼を頂いたBさんの場合。
夫名義の築30年以上のマンションに一人住まいのBさん。
Bさんのマンションの一室が、
マンションの所有者全員の共有の集会所になっていました。
マンションの部屋(専有部分の建物といいます)と
その敷地の共有部分の移転登記と併せて、
集会所の共有持分の移転登記も申請しました。
ところが、この集会所の登記内容を確認したところ、
Bさん以外の多くの共有者について、
相続登記が行われていないことが判りました。
既に亡くなっている方の名義のままになっている持分登記が
いくつも放置されていました。
もちろんBさんにはなす術もないのですが、
後々、トラブルになる可能性があると感じました。
この例のように、共有の不動産について、
相続登記の漏れが起きる場合として、他には、
隣地所有者と共有の私道についての共有持分があります。
事例3)父親との共有の土地の相続登記のご相談を頂いたCさんの場合。
Cさんは、父親と二人で購入資金を出し合って購入し、
2分の1の割合で共有している土地の上に、単独名義で自宅を建て、
長年同居してきました。
この度、父親が亡くなり、その持分を自分に移したいと、
ご相談に来られました。
ところが、相続登記に必要な戸籍を集めた結果、
父親には前婚の妻との間に子がいることが判明したのです。
Cさんは、その腹違いの兄弟の存在は何となく知っていましたが、
まさか共同相続人になるとは想像もしていなかったようです。
Cさんは、現在も、兄弟との間で協議がまとまっていません。
このように、
父または母のいずれか一方だけを同じくする兄弟を「半血兄弟」といいます。
共同相続人の中に半血兄弟がいるために、
遺産分割協議が難航する例は、共有の不動産に限ったことではありません。
しかし、Cさんの様に、結果的には、
単独所有である建物についてまで将来売却等が困難になってしまう。
こんな事態が起こりうるのです。
上のような事例のほかにも、
例えば、
共有者の中の一人に認知症などによる判断能力の低下があったりすることでも
問題が生じます。
親子で共有している土地建物を売却して、
認知症の親を入居させるための資金を捻出しようとしても容易ではない。
多くの方から聞くお話です。
もちろん、相続で問題となるのは、共有の場合だけではありません。
共有の場合でなくても、土地と建物の所有者が異なる場合、
例えば、親の土地の上に、子の中の一人が建物を建てることもあるでしょう。
ただ、これに共有という要素が加わることによって、
一層トラブルが深刻化することがあります。
======================================================================
将来のトラブルを避けるためには、
できる限り共有ではなく、単有・単独所有にすることが有効です。
それでも、敢えて、共有にするということであれば、
不動産を共有することのリスクを予め十分認識し、
遺言などの準備をすることをお勧めします。

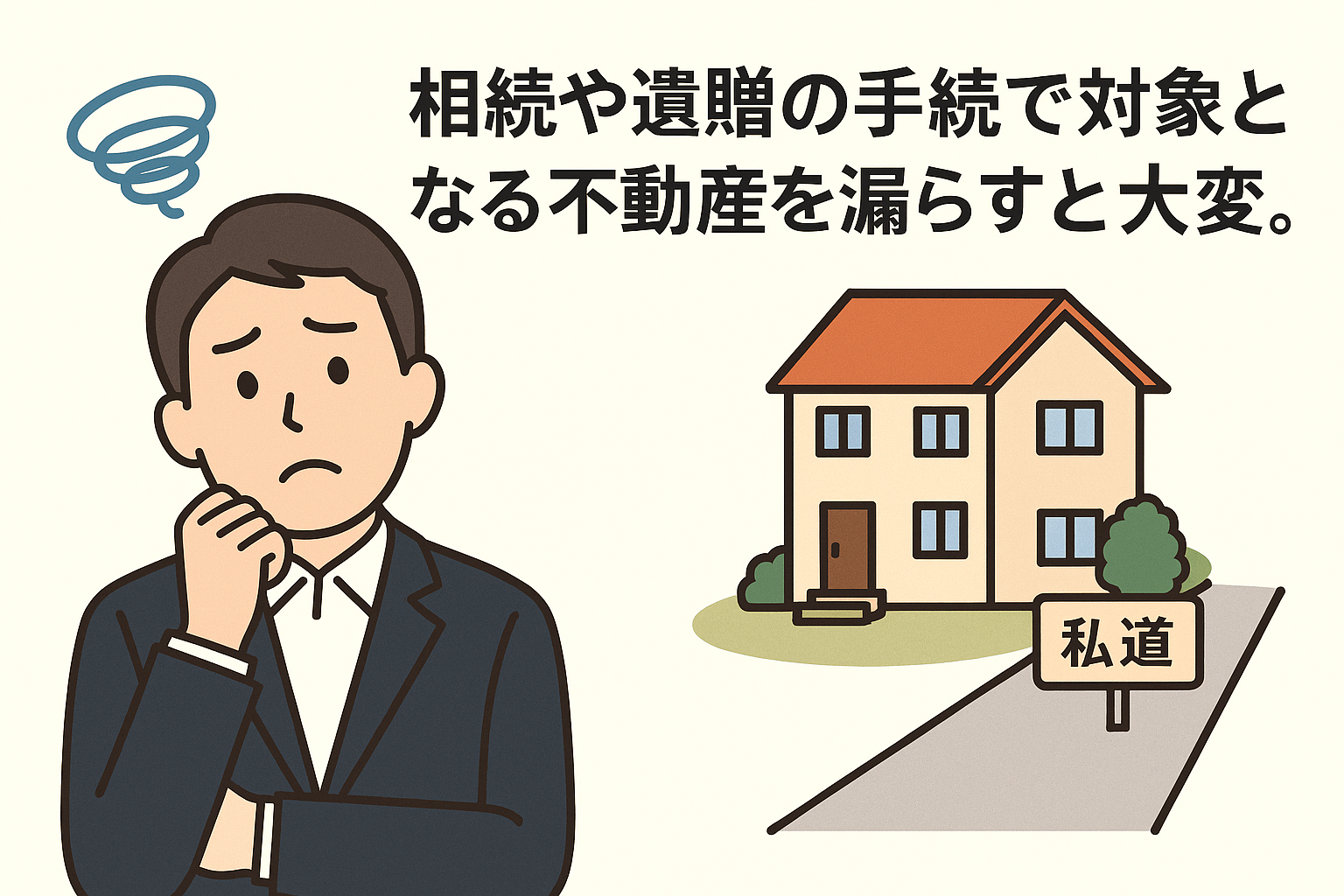

コメント