預貯金の名義人が亡くなった時の口座凍結に備えましょう!
第一章:佐藤家の悲劇
佐藤太郎さん(仮名)が突然の心筋梗塞で亡くなったのは、ある晴れた春の日のことでした。
残された妻の花子さんと大学生の娘・美咲さん。悲しみに暮れる間もなく、葬儀の準備に追われます。
「お母さん、葬儀費用どうするの?お父さんの口座から出せばいいよね」
美咲さんの何気ない一言に、花子さんは銀行へ向かいました。夫婦で長年使ってきた銀行の窓口で、キャッシュカードと通帳、そして死亡診断書を提示します。
「申し訳ございません。口座が凍結されておりますので、お引き出しには応じかねます」
銀行員の言葉に、花子さんは耳を疑いました。
「でも、私は妻です。葬儀費用も必要なんです!」
「相続人全員の同意書と戸籍謄本、遺産分割協議書などをご用意いただかないと…」
花子さんは呆然としました。電気・ガス・水道の引き落とし口座も、すべて夫名義。これらも全部止まってしまうというのです。
第二章:「口座凍結」という名の壁
実は、この口座凍結、法律で定められているわけではありません。
預貯金は法律的には「可分債権」といって、相続人それぞれが自分の相続分を単独で請求できるはずのものなんです。
太郎さんのケースでいえば、妻の花子さんと娘の美咲さんがそれぞれ2分の1ずつ、単独で請求できるのが本来の法律の定めです。
では、なぜ銀行は凍結するのでしょうか?
答えは単純です。銀行のリスク回避、つまり保身のためです。
一部の相続人に支払った後で、他の相続人から「勝手に払うな!」とクレームを受けたり、訴訟を起こされたりするリスクを避けたいのです。さらに言えば、なるべく解約に応じないで預金額を減らしたくない、という事情もあるでしょう。
多くの人が銀行や郵便局を、まるで市役所のような公共機関だと錯覚しています。しかし、相続という場面では、彼らが決して利用者側に立っていないことが露呈してしまうのです。
第三章:花子さんの苦闘
花子さんは必死で書類を集め始めました。
- 亡くなった夫の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
「まるで不動産の名義変更みたい…いや、それ以上かも」
銀行によっては、公正証書遺言があっても相続人全員の実印付同意書を要求するところもあるそうです。
書類集めに数週間。その間、葬儀費用は花子さん自身の貯金から工面しました。生活費も同様です。
第四章:隣の田中さんの「禁断の方法」
「花子さん、実はね…」
近所の田中さんが、こっそり教えてくれました。自分の夫が亡くなったとき、キャッシュカードで死亡届を出す前に預金を引き出したというのです。
「え、でもそれって…」
実はこれ、非常に危険な行為なんです。
相続人が相続財産を処分すると、「単純承認」したとみなされ、亡くなった人の借金も含めてすべて相続する意思だと判断されてしまいます。これを「法定単純承認」といいます。
もし夫に隠れた借金があったら?預金以上の借金だったら?
相続放棄や限定承認という選択肢が、完全に失われてしまうのです。
葬儀費用だけなら「処分」にあたらないともいえますが、生活費となると話は別。リスクが高すぎます。
第五章:救いの手—仮払い制度
「花子さん、2019年にできた新しい制度があるんですよ」
司法書士の私が花子さんに説明したのが、仮払い制度です。
1. 裁判によらない仮払い制度
他の相続人(この場合は娘の美咲さん)の承諾不要で、単独で利用できます。
引き出せる金額は「150万円」または「預金額×1/3×法定相続分」のいずれか低い方。
太郎さんの口座に600万円あったとすれば:
- 600万円×1/3×1/2=100万円
花子さんは100万円まで引き出せることになります。
2. 裁判上の仮払い制度
もし100万円では足りない場合は、裁判所に申し立てることで、より多くの金額を仮払いしてもらえる可能性があります。
ただし注意点があります。仮払い金は「もらい得」ではありません。後の遺産分割協議で、相続分から差し引かれて調整されます。あくまでも「仮」の措置なのです。
今日のポイント:備えあれば憂いなし
花子さんの苦労を見ていた美咲さんは、こう言いました。
「お母さん、私たちも将来のために何か準備しておかないとね」
預貯金は、ほとんどの人が持っている財産です。
そして、名義人が亡くなれば必ず口座が凍結されることを忘れてはいけません。
では、どう備えるべきでしょうか?
- 夫婦それぞれが自分名義の口座で生活費を管理する
- 葬儀費用程度の現金は手元に用意しておく
- 家族で財産状況を共有しておく
- 仮払い制度の存在を知っておく
- 必要に応じて専門家(司法書士や弁護士)に相談する
正しい知識と適切な準備があれば、私たちは大切な財産を守り、円滑に次世代へ引き継ぐことができるのです。
「いざというとき」は、必ず訪れます。その日のために、今できることから始めませんか?

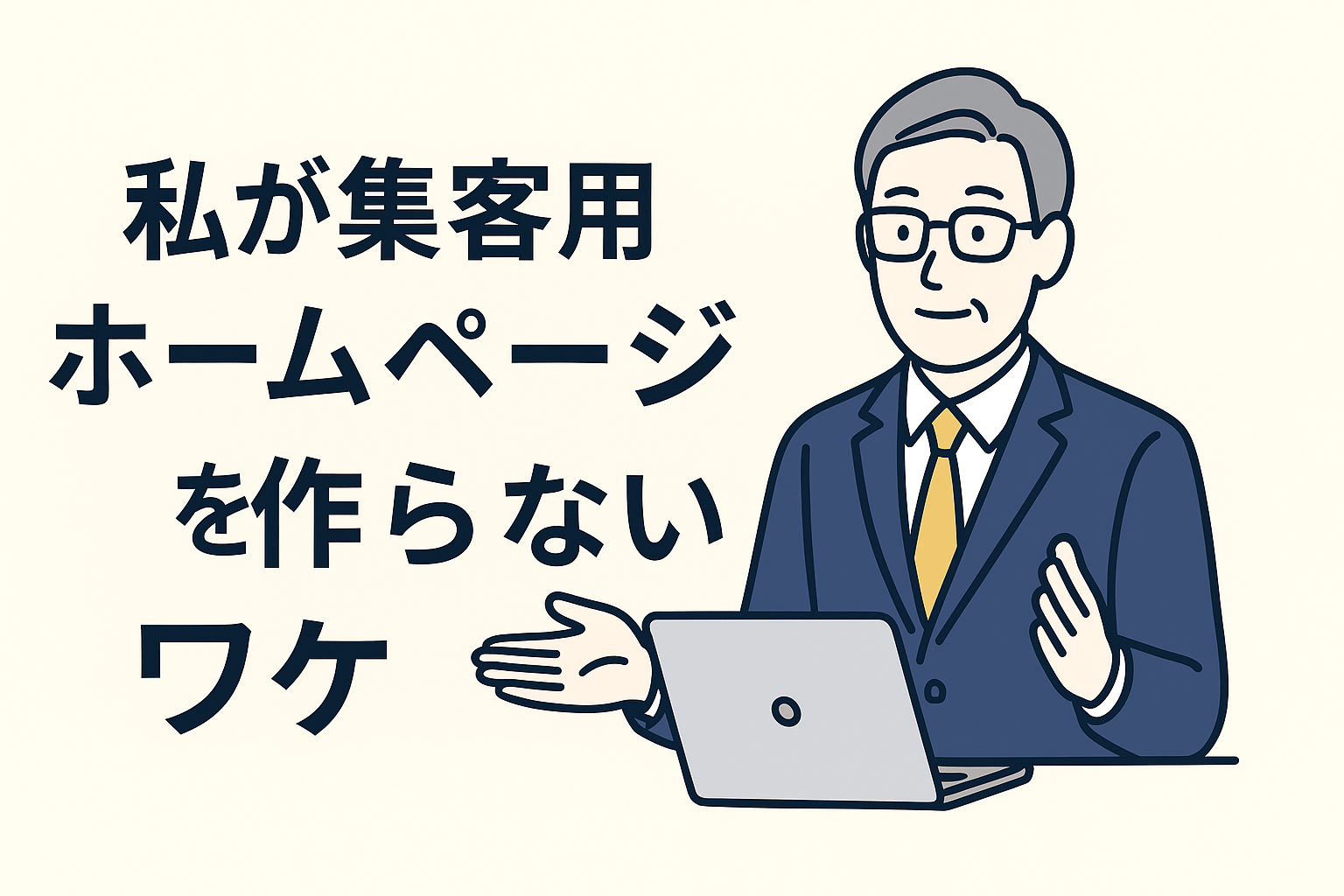

コメント