副業の波が来ています
こんにちは、社会保険労務士の小椋です。
ここ数年、私の事務所に寄せられる相談で最も増えているのが「社員の副業」に関するものです。「働き方改革」の流れを受け、多くの企業様が副業解禁を検討されていますが、同時に「どのようなリスクがあるのか」「どう対応すべきか」と悩まれています。
先日も、長年お付き合いのある製造業A社の人事部長から急な相談を受けました。
「小椋先生、うちも副業を認めることになったんです。でも、何から手をつければいいのか…」
そこで今回は、私がA社をはじめ多くの企業様にお伝えしている「社員の副業を認める際の注意点」について、実務的な観点からお話しします。
第1のアドバイス:就業規則は必ず整備を
まず取り組むべきは就業規則の整備です。多くの企業様の就業規則には、「従業員は会社の許可なく他の職業に従事してはならない」といった副業禁止条項が入っています。
「A社さん、まずはこの条項を見直しましょう。ただし、単純に削除するだけではリスクが高いですよ」
私が提案するのは、以下のような規定の整備です:
- 副業の届出制または許可制の導入 「社員が副業を始める際は、事前に会社に届け出る(または許可を得る)ものとする」
- 禁止・制限される副業の明確化 「競合他社での勤務、当社の事業と競合する業務、当社の信用・利益を損なう恐れのある業務については、副業として認めない」
- 副業の変更・終了時の報告義務 「副業の内容に変更が生じた場合、または副業を終了した場合は速やかに報告すること」
A社の就業規則改定に際しては、このような条項を盛り込み、労働基準監督署への届出も忘れずに行いました。
第2のアドバイス:労働時間管理と健康配慮は最重要課題
副業を認める際に最も注意すべきなのが、労働時間の管理です。多くの企業様が見落としがちですが、労働基準法では複数の職場で働く場合、その労働時間は通算されます。
「A社の佐藤部長、これは重要なポイントです。たとえば御社で8時間勤務した後、社員が副業で4時間働けば、その日は12時間労働となり、時間外労働の対象になります。36協定の上限を超えるリスクもありますよ」
対策としては:
- 副業の労働時間の申告制度 「月に一度、副業での労働時間を報告してもらう仕組みを作りましょう」
- 健康状態のモニタリング 「定期的な面談や健康診断を通じて、過重労働の兆候がないか確認を」
- 本業への影響評価 「明らかに疲労が見られる場合や、本業のパフォーマンスが低下している場合は、個別に相談する体制を」
A社では、私のアドバイスを受けて「副業労働時間報告書」を作成し、月次での報告を義務付けました。これにより労働時間の把握と健康管理の両面をカバーしています。
第3のアドバイス:職務専念義務・秘密保持義務の再確認を
副業を認めると、情報管理のリスクが高まります。過去に私が対応したケースでは、社員が副業先で自社の営業秘密を話してしまい、大きなトラブルになったこともあります。
「職務専念義務や秘密保持義務は、副業を認めても消滅するわけではありません。むしろより重要性が増します」
私が提案する対策は:
- 情報管理に関する誓約書の取得 「副業開始時に、改めて秘密保持に関する誓約書を取得することで意識付けを」
- 定期的な教育研修の実施 「情報管理の重要性について、定期的に研修を行いましょう」
- 違反時の対応の明確化 「秘密保持義務違反が発生した場合の懲戒処分等を明確にしておくことも抑止力になります」
A社では、副業申請書と一緒に「副業における情報管理に関する誓約書」の提出を義務付け、社員の意識向上につなげています。
第4のアドバイス:副業内容の把握と定期的な確認を
「小椋先生、どこまで社員の副業に介入していいものでしょうか?」
これは多くの企業様から受ける質問です。プライバシーへの配慮は必要ですが、会社として最低限の把握は必要です。
私のアドバイスは:
- 副業の基本情報の報告 「業務内容、就業先(自営の場合はその旨)、予定就業時間などの基本情報は把握しましょう」
- 定期的な状況確認 「四半期に一度など、定期的に副業状況の報告を求めるとよいでしょう」
- 変更時の報告ルール 「副業内容や就業時間に大きな変更があった場合は、その都度報告を求めましょう」
A社では、「副業状況報告書」のフォーマットを作成し、3ヶ月ごとの報告を制度化しました。これにより、社員の副業状況を適切に把握できています。
第5のアドバイス:税金・社会保険の情報提供を
副業に取り組む社員の多くが頭を悩ませるのが、税金や社会保険の問題です。
「このあたりは会社の義務ではありませんが、情報提供をすることで社員の不安を減らし、トラブルを予防できます」
具体的には:
- 確定申告に関する基本情報の提供 「副業収入が年間20万円を超える場合は確定申告が必要なこと、基礎控除や経費計上の仕組みなど」
- 社会保険への影響の説明 「副業先でも厚生年金・健康保険に加入する可能性がある場合の手続きなど」
- 専門家への相談機会の提供 「必要に応じて、税理士や社労士への相談機会を設けることも効果的です」
第6のアドバイス:想定外のリスクにも備えを
最後に、あらゆるリスクを想定した対策の準備をお勧めします。
「小椋先生、他にどんなリスクがありますか?」というA社からの質問に対し、以下のようなケースを説明しました:
- 反社会的勢力との関わり 「副業先が反社会的勢力と関係している可能性も…そのための確認体制を」
- 会社名の不正使用 「『〇〇会社の社員です』と肩書きを使った営業活動などへの対策を」
- SNS等での情報発信リスク 「副業でのSNS活動が会社のイメージに影響する可能性も考慮を」
- 副業先での労災事故 「副業先での労災は、本業の業務にも影響する可能性があります」
A社では、これらのリスクも含めた「副業リスク管理ガイドライン」を作成し、社内で共有しています。
バランスの取れた副業制度の構築を
副業制度の導入から半年が経過したA社。先日、人事部長から嬉しい報告がありました。
「小椋先生、おかげさまで大きなトラブルなく副業制度が定着しています。若手社員の満足度も上がり、新しいスキルを身につけて本業にも活かしている社員も出てきました」
私が強調したいのは、副業は「禁止するもの」から「適切に管理するもの」へと変わってきているということです。時代の流れに合わせ、企業と社員双方にメリットをもたらす形で副業を認めていくことが、これからの人事労務管理には求められています。
【顧問社労士・小椋の実務チェックリスト】
1. 就業規則の整備
- □ 副業の可否・条件に関する規定
- □ 届出制・許可制の手続き規定
- □ 禁止する副業内容の明記
- □ 違反時の対応に関する規定
2. 労働時間・健康管理
- □ 副業労働時間の報告制度
- □ 過重労働防止のモニタリング
- □ 健康状態確認の仕組み
- □ 労働時間通算に関する社員教育
3. 情報管理・義務の徹底
- □ 秘密保持に関する誓約書
- □ 情報管理研修の実施
- □ 職務専念義務の再確認
- □ コンプライアンス教育
4. 副業状況の把握
- □ 副業申請書のフォーマット
- □ 定期報告の仕組み
- □ 変更時の報告ルール
- □ 本業への影響評価方法
5. 税務・社会保険の対応
- □ 確定申告に関する情報提供
- □ 社会保険の取扱い説明
- □ 専門家相談の機会提供
- □ Q&A資料の作成・共有
6. リスク管理体制
- □ 想定リスクの洗い出し
- □ 対応フローの整備
- □ 責任部署・担当者の明確化
- □ 定期的な制度見直し
副業制度を導入する際は、このチェックリストを参考に、貴社の状況に応じた対応をご検討ください。 もし、より詳しいアドバイスが必要な場合は、当職にご相談ください。

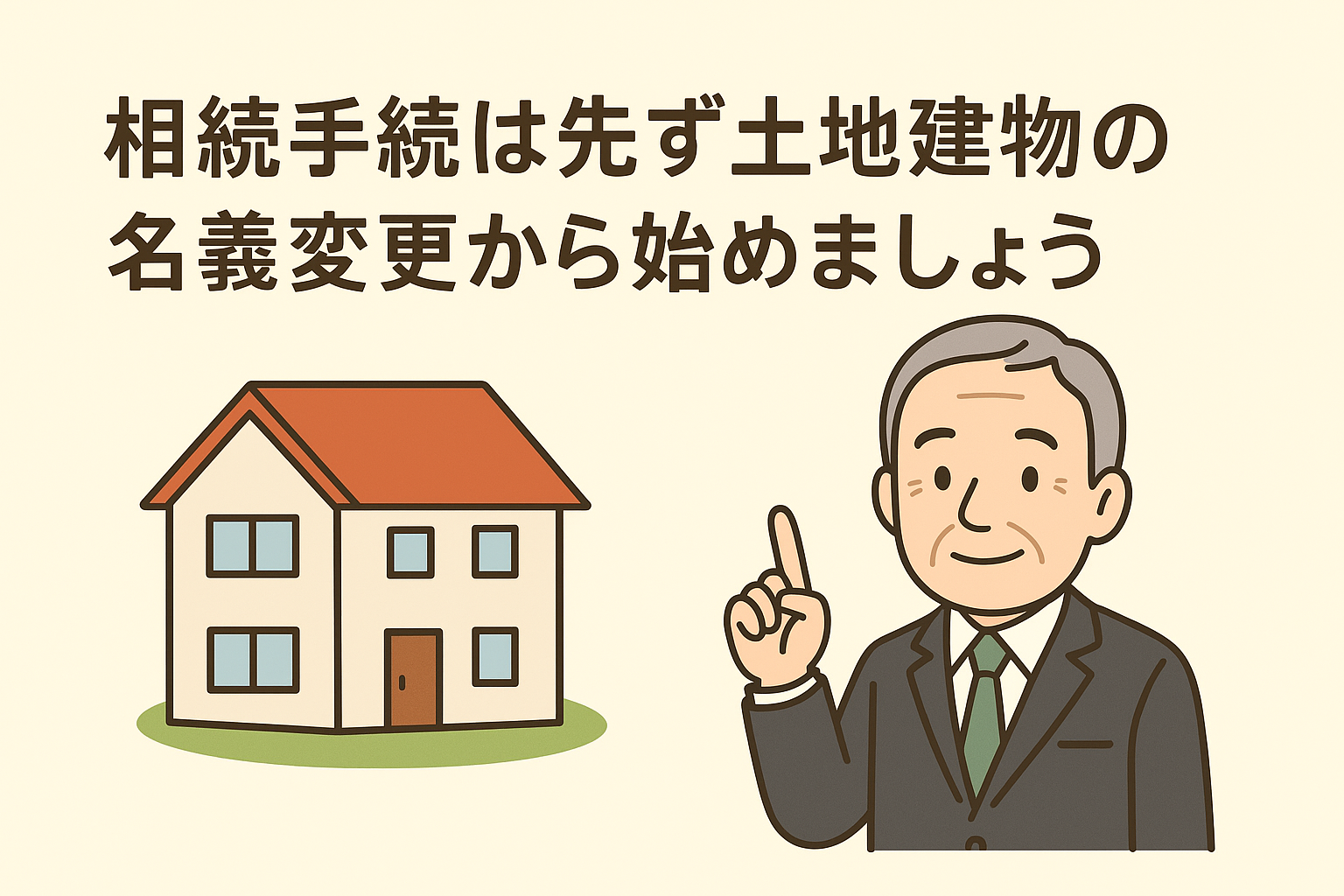
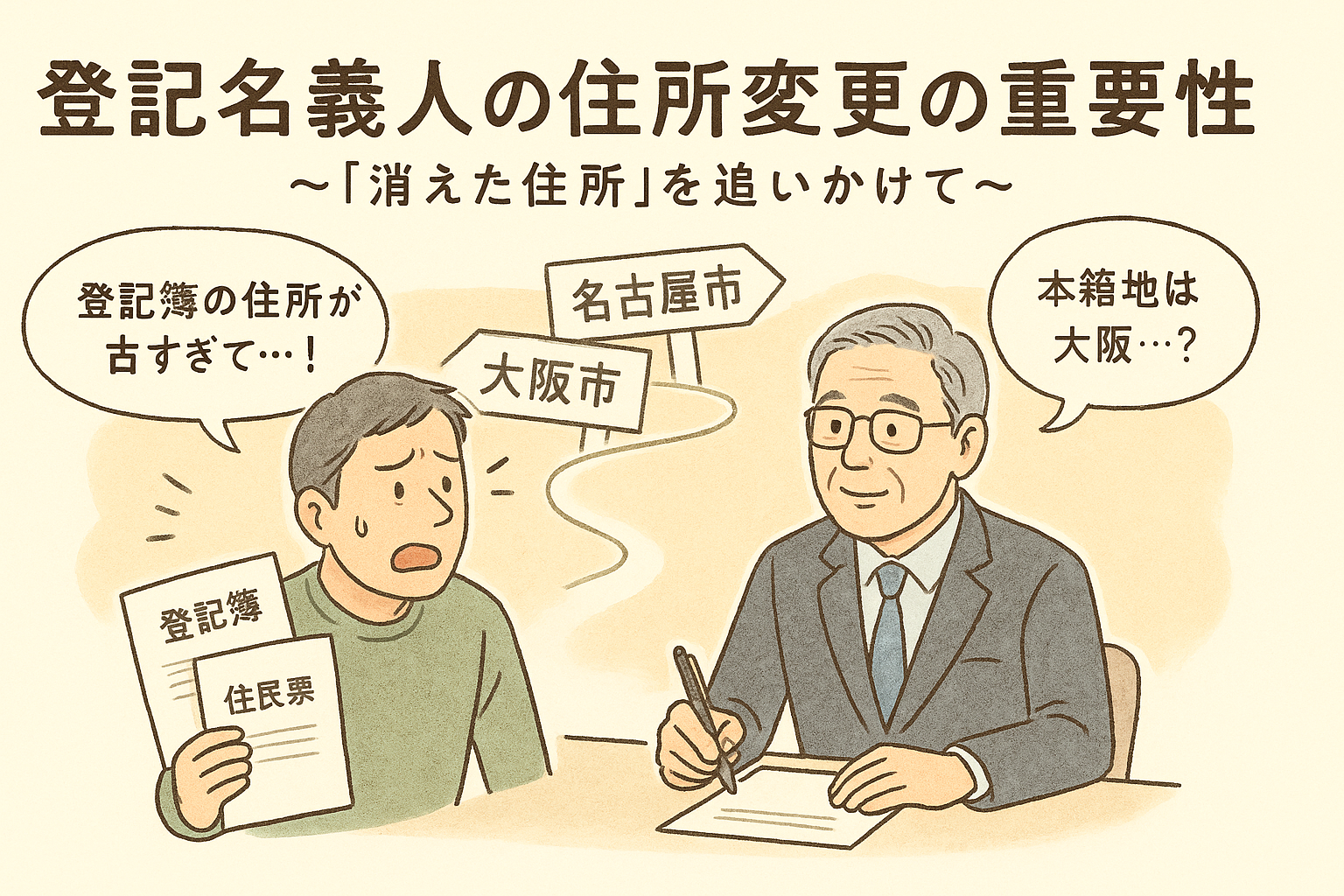
コメント