自筆の遺言書はいきなり開封してはいけません!
封筒を開けようとした、その瞬間
祖父が亡くなって三日後のことだった。
遺品整理を手伝っていた私は、書斎の引き出しの奥から、見覚えのある祖父の筆跡で「遺言書」と書かれた封筒を見つけた。
「これ、おじいちゃんの遺言書だ!」
思わず声を上げると、居間にいた母と叔父が駆けつけてきた。三人で封筒を囲み、私は自然と封を開けようと手を伸ばした。
「待って!」
母が私の手を制した。
「開けちゃダメなの。まず家庭裁判所に持っていかないと」
知らなかった「検認」という手続き
母の説明によれば、自筆の遺言書には「検認」という手続きがあるという。家庭裁判所に提出して、正式な確認を受けなければならないらしい。
「勝手に開封したら、5万円以下の過料を取られることもあるのよ」
まさか遺言書を開けるだけで罰金を科される可能性があるなんて。危うく大きな失敗をするところだった。
その日、私たちは遺言書を大切に保管し、翌週、祖父の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立てをすることにした。
家庭裁判所での検認手続き
申立てに必要な書類を揃えるのは少し手間がかかった。戸籍謄本や住民票など、必要な書類を一つ一つ取り寄せ、郵送で裁判所に送った。
二週間ほどして、裁判所から検認期日の通知が届いた。母だけでなく、叔父や遠方に住む叔母にも同じ通知が送られているという。「これで、みんなが遺言の存在を知ることになるのね」と母が呟いた。
検認期日の当日、私は母に付き添って家庭裁判所へ向かった。叔父も来ていたが、叔母は仕事の都合で欠席だった。
小さな部屋に案内され、裁判官の前で初めて祖父の遺言書が開封された。裁判官は丁寧に遺言書の状態を確認し、筆跡や押印について母と叔父に質問した。
「これは、お父様の筆跡で間違いありませんか?」
「はい、間違いありません」
そうやって一つ一つ確認していく様子を見ながら、私はこの手続きの意味を理解した。これは遺言書の偽造や変造を防ぐための、大切な儀式なのだと。
検認が終わって
手続きが終わると、遺言書には「検認済証明書」が添付されて返却された。欠席した叔母には後日、検認済みの通知が送られるという。ただし、遺言書のコピーが配布されるわけではないので、内容を知りたければ直接聞いてもらう必要があるらしい。
帰り道、母が言った。
「公正証書で作っておいてくれたら、こんな手間はかからなかったんだけどね」
確かに、公正証書遺言や法務局で保管する自筆証書遺言なら、検認は不要だという。祖父はきっと、家族に面倒をかけたくなくて遺言書を書いてくれたのだろう。でも、正しい手続きを知らなければ、その優しさが逆に混乱を招いてしまう。
私が学んだこと
あの日、もし母が止めてくれなかったら、私は何も知らずに封を開けていただろう。そして知らず知らずのうちに、法律に違反していたかもしれない。
遺言書は、ただの手紙ではない。法的な効力を持つ大切な書類だ。だからこそ、正しい手順を踏むことが何より重要なのだと、今回の経験で身をもって学んだ。
もし、あなたの身近な人が遺言書を遺していたら──あるいは、これから遺言書を作ろうと考えているなら──ぜひこの「検認」という手続きのことを思い出してほしい。
そして可能であれば、公正証書遺言という選択肢も検討してみてほしい。残される家族のためにも、それが一番確実で、優しい方法なのだから。
※この記事は、自筆証書遺言の検認手続きについての理解を深めるための創作ストーリーです。実際の相続手続きについては、司法書士にご相談ください。
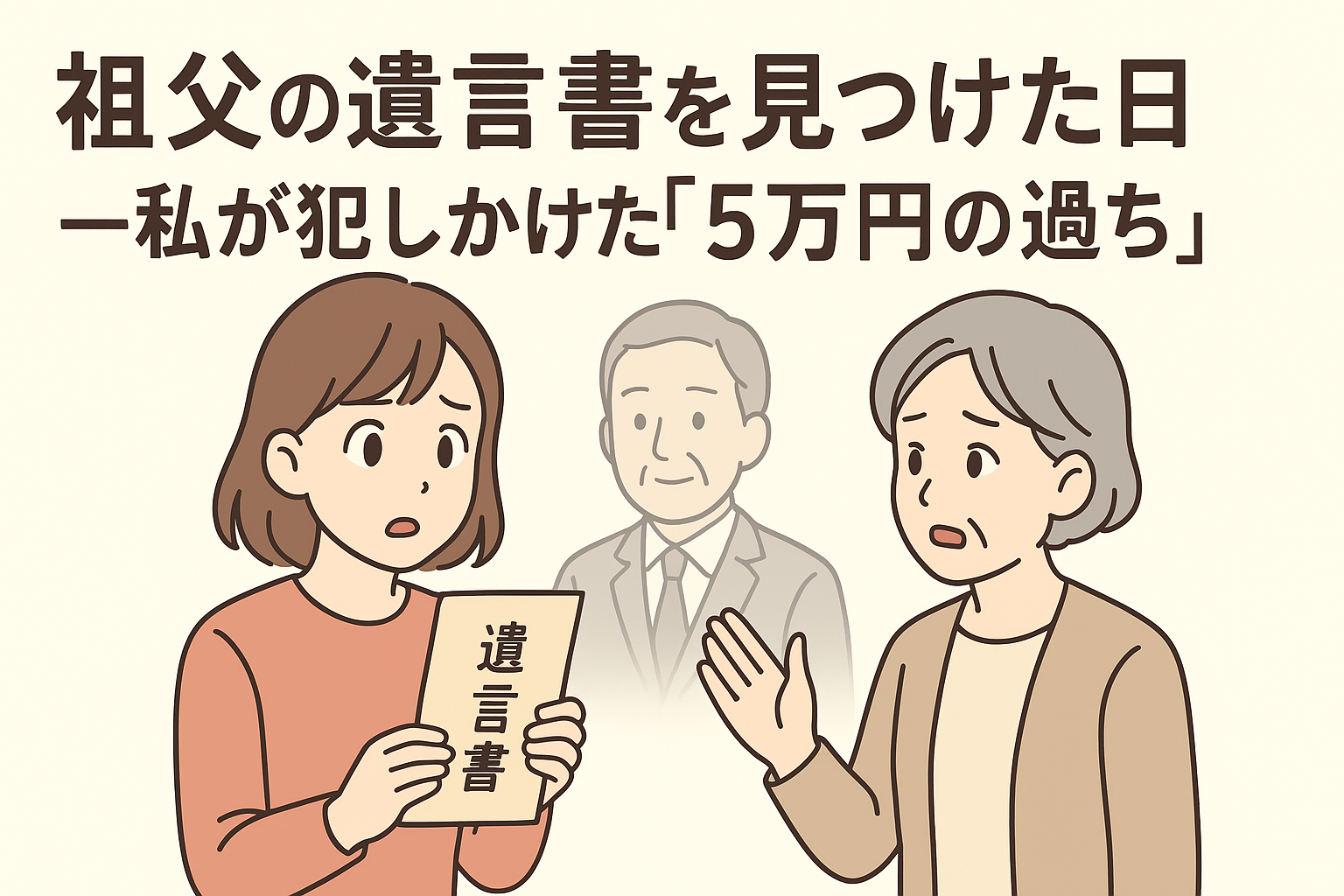
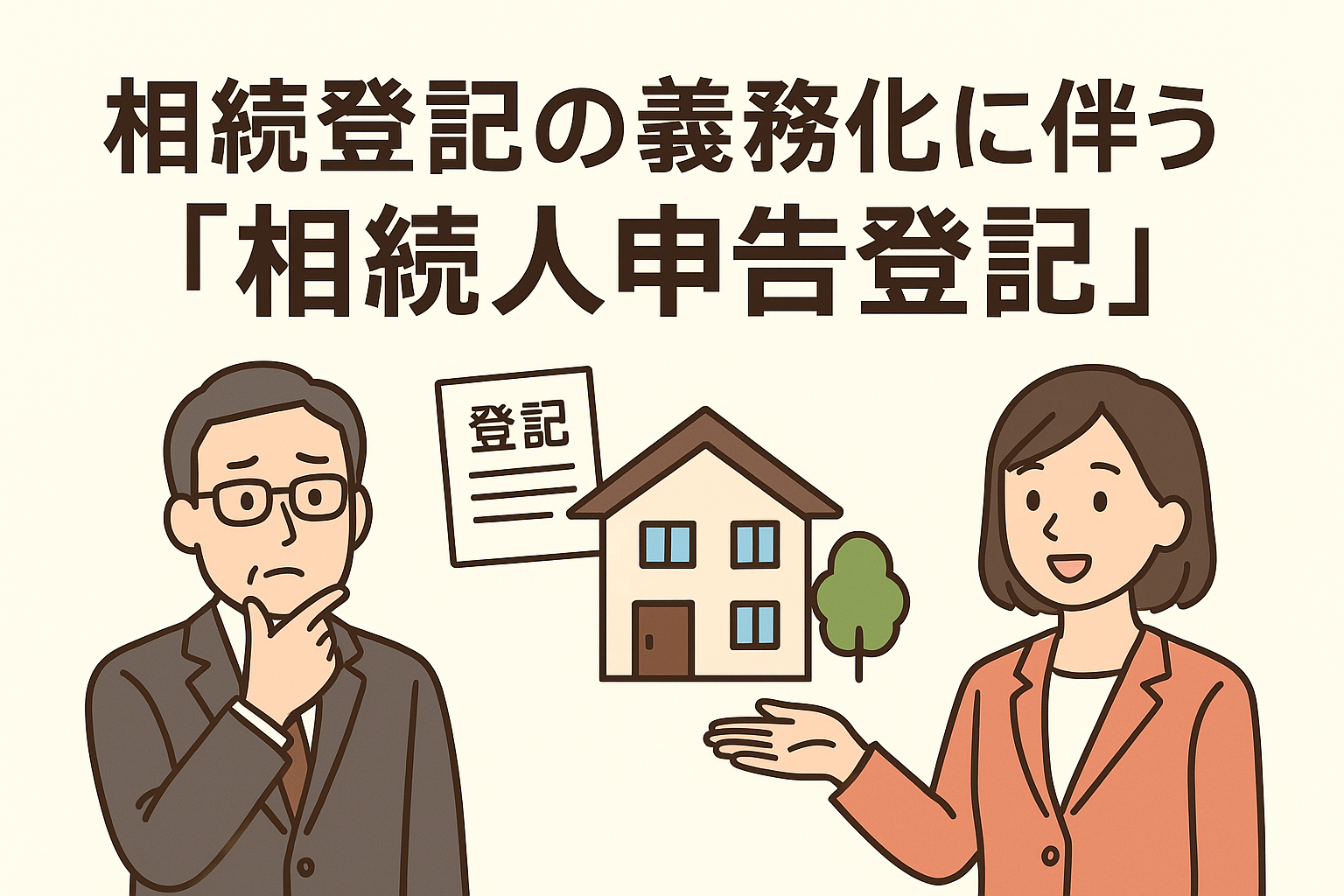
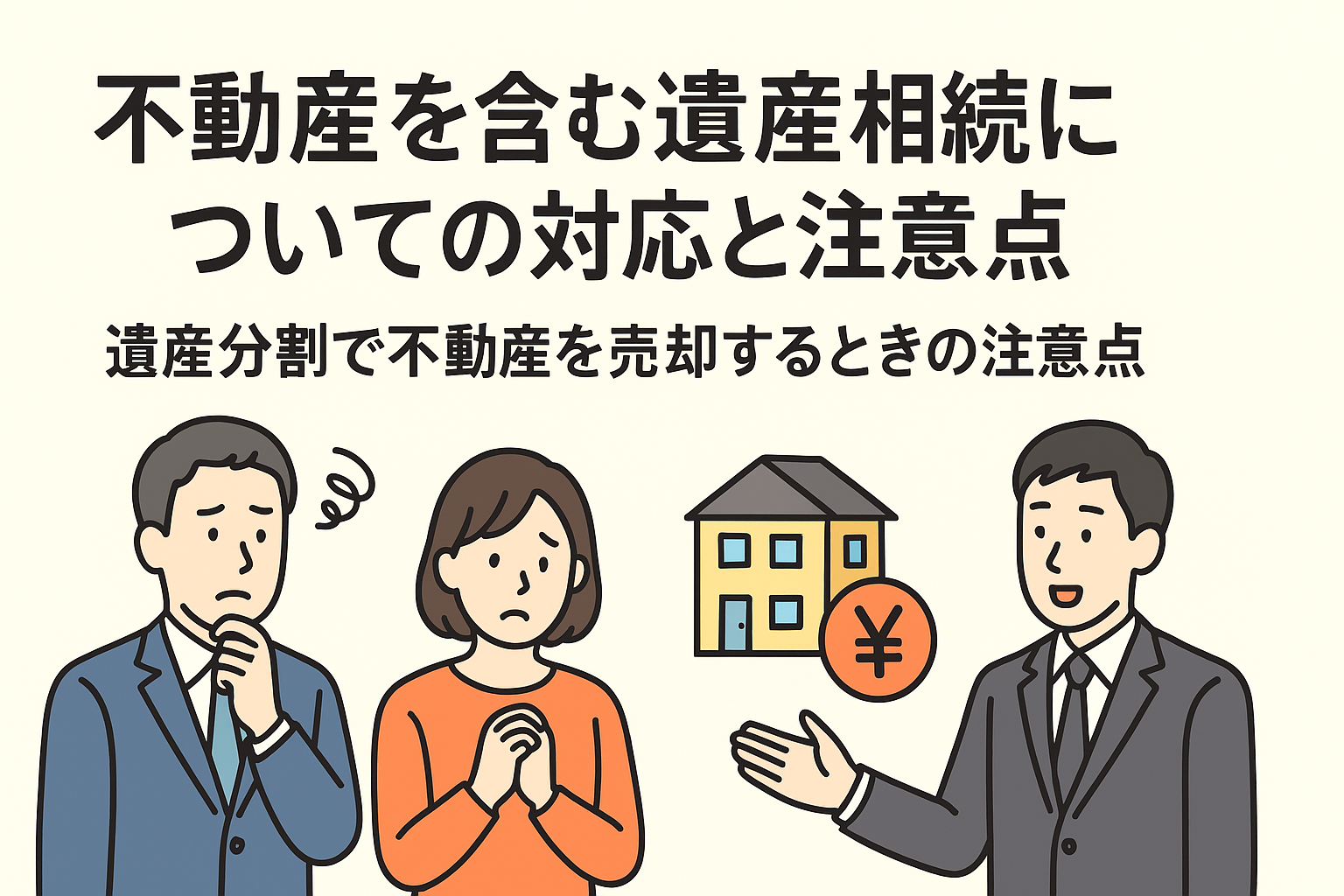
コメント