プロローグ:終活ブームの陰で
桜が散り始めた4月のある日、私の事務所に一本の相談電話が入りました。声の主は70代後半と思われる女性で、「遺言について相談したい」とのことでした。
近頃の終活ブームで、遺言に関する相談は確かに増えています。しかし、その多くは「エンディングノート」と「遺言」を混同されている方が少なくありません。
エンディングノートは、確かに家族への想いや希望を記す大切なツールです。しかし、法的な拘束力はありません。一方、遺言は法律で定められた要件を満たせば、強い法的効力を持つ重要な文書なのです。
第一章:遺言が必要な人、不要な人
相談に来られる方によく説明するのは、遺言の必要性は人それぞれ異なるということです。大きく分けて3つのタイプがあります。
最も遺言が必要な方は、子のない夫婦です。配偶者が亡くなった時、残された方は義理の兄弟姉妹と遺産分割の協議をしなければならない可能性があります。
できれば遺言を作った方が良い方は、複数の相続人がいる場合です。特に法定相続とは異なる相続を希望する場合、例えば「長男にだけ不動産を継がせたい」といったケースでは遺言が必要になります。
遺言の必要性が低い方は、財産が極端に少ない方や、法定相続人が一人しかいない方です。
しかし、この最後のケースでも、思わぬ事情で遺言が必要になることがあります。
第二章:林ミツエさんの物語
9年前の春、私のもとを訪れた林ミツエさん(仮名)のケースは、まさにその典型例でした。
ミツエさんは一人娘の久美子さん(仮名)を持つ母親でした。通常であれば、遺言の必要性は低いはずです。しかし、ミツエさんの表情は深い悲しみと決意に満ちていました。
「娘には一切財産を渡したくないんです」
その言葉の背景には、30年という長い年月に渡る家族の物語がありました。
久美子さんは30年前に離婚し、当時12歳と10歳だった二人の娘を母親であるミツエさんに預けたまま、家を出て行ってしまったのです。
「あの子たちが不憫で…」
ミツエさんは生命保険のセールスで安定した収入があったため、経済的な困窮はありませんでした。しかし、幼い孫たちを置いて去っていく娘の姿を見て、深い失望を感じたのです。
第三章:愛の選択
それから30年間、ミツエさんは親代わりとなって孫たちを育て上げました。そして現在は、次女の孫夫婦と同居し、手厚い介護を受けながら穏やかな日々を送っていました。
「今の孫たちがいなければ、私はとっくに一人ぼっちでした。本当の娘のように私を支えてくれています」
ミツエさんの決断は明確でした。法律上の相続人である久美子さんではなく、長年自分を支えてくれた孫に全財産を残したい—それが彼女の願いでした。
第四章:遺言に込められた想い
ミツエさんの公正証書遺言の末尾には、次のような付言が記されました。
『遺言者には、相続人となるべき者として、一人娘の久美子がいますが、永年音信不通で現在も絶縁状態が続いています。そのため、久美子には、財産を一切相続させたくありません。
現在、遺言者は、私が所有する建物で孫夫妻と同居し、いろいろ面倒を見てもらっています。今後も何かと頼りにせざるを得ないので、その孫に財産全てを遺贈したいと考えています。
後日財産を巡り紛争が生じないことを念じ、この遺言を作成することにしました。』
この文章には、ミツエさんの30年間の想いが凝縮されていました。法律的な効力だけでなく、家族への愛と感謝、そして未来への願いが込められていたのです。
エピローグ:想いが実現した時
遺言作成から5年後、ミツエさんは静かに息を引き取りました。遺言通り、全財産は孫に引き継がれ、現在に至るまで久美子さんからの遺留分請求もありません。
ミツエさんのケースは、私たちに重要なことを教えてくれます。単独相続の場合でも、法定相続を望まない事情があれば、遺言は必要不可欠だということです。
生前贈与という方法もありますが、多額の贈与税を考えれば現実的ではありません。遺言こそが、ミツエさんの想いを実現する最良の手段だったのです。
あなたの想いを形にするには
遺言は単なる法的文書ではありません。それは、残される家族への最後のメッセージであり、長い人生で培った価値観や愛情を形にする手段なのです。
ミツエさんの物語は、遺言が持つ真の意味を私たちに教えてくれています。大切なのは財産の多寡ではなく、その人の想いをいかに適切に実現するかということなのです。
もしあなたも、法定相続とは異なる想いをお持ちなら、司法書士にご相談されることをお勧めします。あなたの想いを確実に伝える遺言が、きっと見つかるはずです。
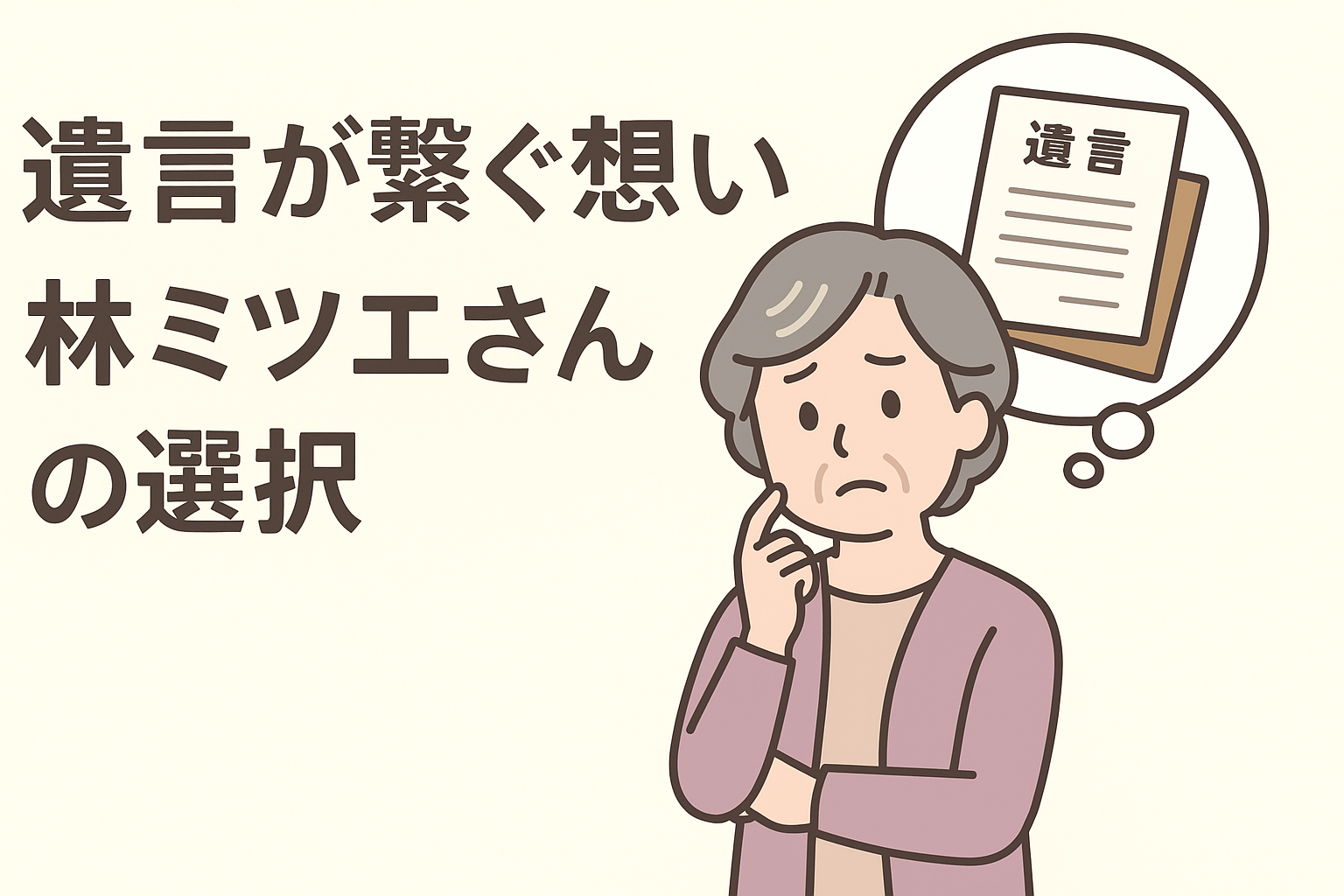


コメント