こんにちは、社会保険労務士の小椋です。
今回は、経営者の皆さまが頭を悩ませることの多い「社員のうつ病」について、実際のご相談を踏まえてお話ししたいと思います。
精神疾患は、雇用管理上で最も難しいテーマ
近年、うつ病や適応障害など、精神疾患を抱える社員の対応に悩む企業が増えています。内科的な病気やケガと異なり、明確な治癒の目安が見えにくいことが、この問題をより複雑にしています。
また、回復の過程が人それぞれであり、医師の「復職可」という診断書が出たからといって、すぐに職場で戦力として復帰できるとは限りません。
実際にあった事例から学ぶ
あるIT企業では、プログラマーとして採用された派遣社員が、うつ病の既往歴を会社に知らせないまま入社しました。入社後まもなく、遅刻や無断欠勤が続き、最終的に本人からうつ病であることが告げられました。
社長は毎朝電話でフォローするなど、誠実に対応しましたが、状況は好転せず、最終的には休職を経て退職という結果になりました。
このようなケースは少なくありません。私の経験上、うつ病から完全に回復し、元通りに職場復帰できたケースはごく稀です。
休職=復職を前提とした制度
企業が社員を「休職」とする場合、その制度の根幹は「いずれは復職する」ことが前提です。休職中であっても、雇用契約は続いていますので、社会保険料の負担は企業・本人ともに発生します。
例えば、1か月まったく出勤がなく無給でも、健康保険や厚生年金の保険料はかかります。本人から直接社会保険料を振り込んでもらうか、復職後に給与から精算する形になります。
傷病手当金の取り扱い
うつ病などで休職中の社員は、健康保険から「傷病手当金」の支給を受けられる可能性があります。これはあくまで 「復職を前提とした支援」です。
申請は原則として本人が行うものですが、希望があれば社労士に手続きの代行を依頼することもできます(※別途手数料がかかります)。
経営者としての“基本方針”を明確にする
一番大切なのは、経営者としての基本方針をしっかりと定めることです。
・その社員との今後の関係をどうしたいのか
・職場に戻ることが、会社にとっても本人にとっても本当に望ましいのか
・その疾患が業務に起因する可能性があるのか(労災の視点)
これらを慎重に見極めたうえで、場合によっては「一度退職して、まずはしっかりと療養する」ことを本人に提案するのも、会社にも本人にも有益な選択肢であると考えます。
最後に
精神疾患への対応は、制度や法律の理解だけでなく、「人としての向き合い方」も問われる難しいテーマです。
困ったときには、ひとりで抱え込まず、ぜひ社労士にご相談ください。会社と社員、双方にとって最善の選択を一緒に考えてまいりましょう。
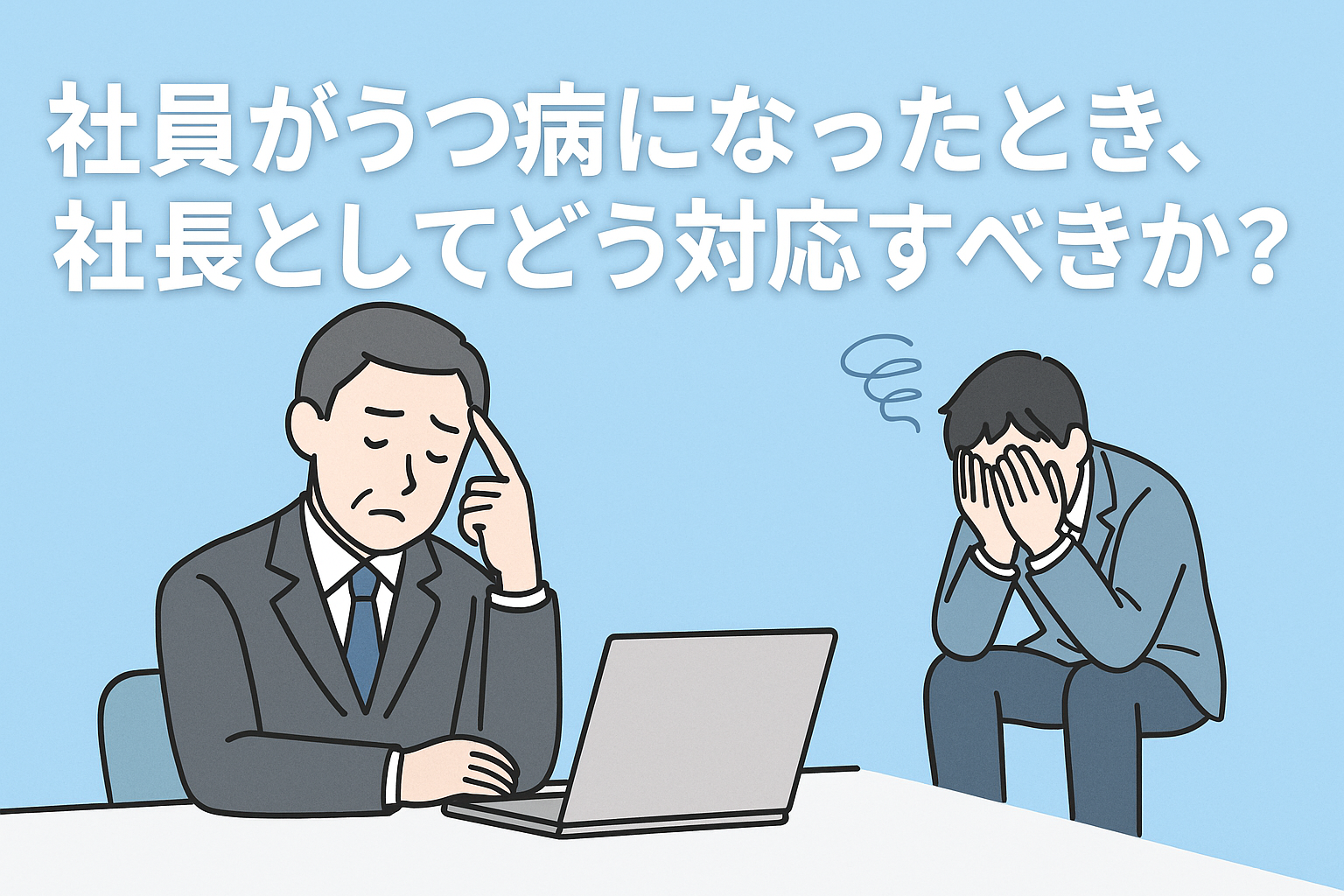
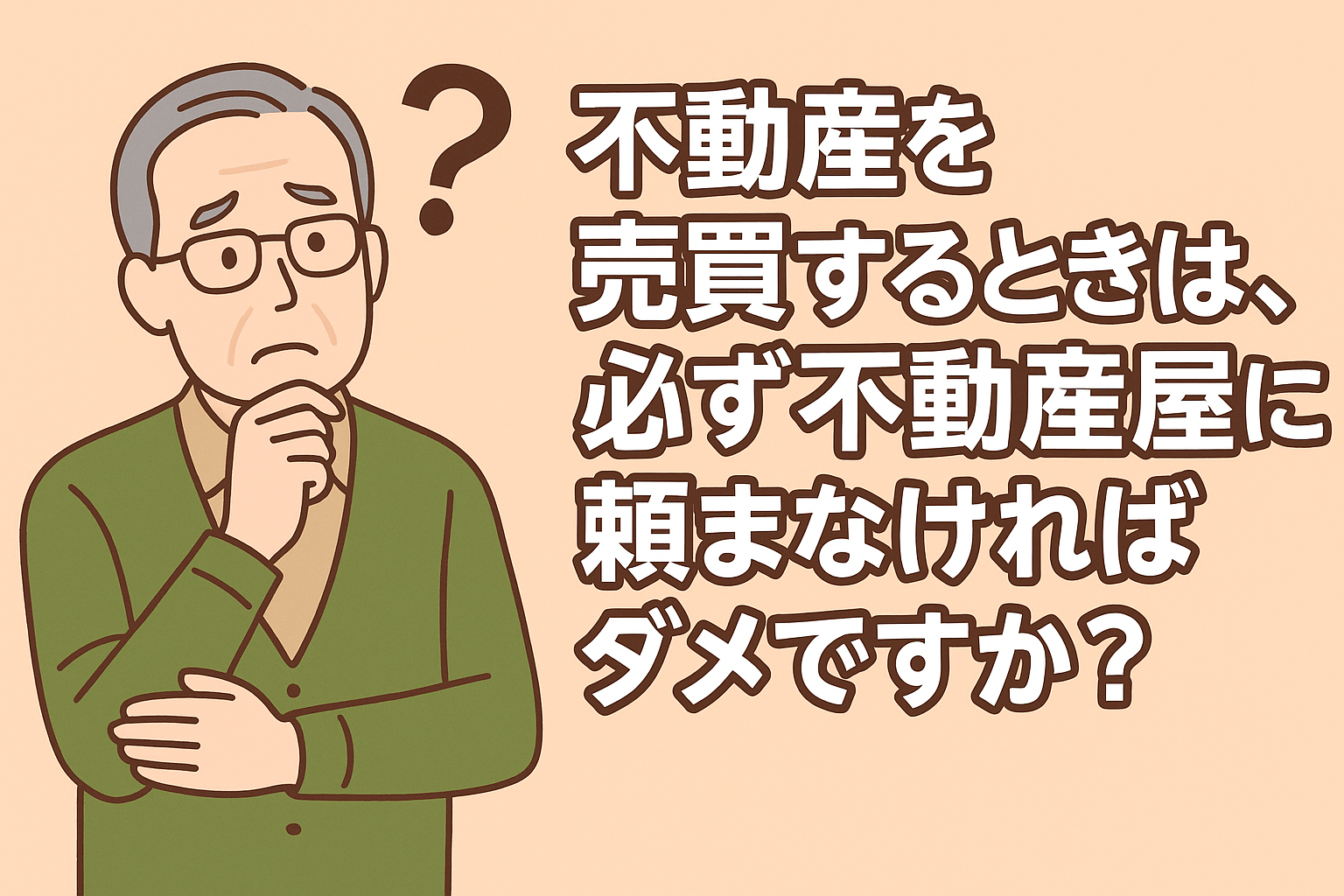

コメント