従業員の退職が決まった際、人事担当者や経営者が頭を悩ませる問題の一つが「残った年次有給休暇(年休)をどう処理するか」です。特に、業務の引き継ぎが必要な重要なポジションの社員が退職する場合、この問題は深刻になります。
今回は、退職時の年休対応について、法的な原則と実務上の対応策を詳しく解説します。
まずは基本を押さえよう:「休日」と「休暇」の違い
年休の話に入る前に、混同しやすい「休日」と「休暇」の違いを整理しておきましょう。
休日:働く義務のない日。会社から出勤を命じられない限り休める日です。労働基準法では、毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上の休日を与えることが義務付けられています。
休暇:本来働く義務のある日に、一定の事由がある場合にその義務が免除される日です。慶弔休暇や産前産後休暇、そして年次有給休暇がこれに該当します。
年次有給休暇は、6ヵ月継続勤務し、全労働日の80%以上出勤した労働者に当然の権利として付与されるものです。パートタイマーなど労働日数の少ない労働者にも、その労働日数に応じて年休が付与されます。
よくある相談ケース
先日、ある顧問先の社長からこんな相談を受けました。
「入社1年の社員から今月末での退職希望が出されているが、消化しきれていない年休をどうすればよいか。業務の引き継ぎが終わっていないので何日かは出勤させたい。それでも残った年休は買い取らなければならないのか?」
このような状況は、多くの会社で起こり得る問題です。法的な観点と実務的な対応の両面から解説していきます。
問題1:退職までに年休を連続取得させる必要があるか?
原則:労働者の自由意思を尊重
年休をいつ取得するかは、原則として労働者の自由意思に委ねられています。使用者が勝手に干渉することは許されません。
ただし、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、使用者は「時季変更権」を行使して、年休の取得時期を変更することができます。単に「忙しいから」という理由では時季変更権は行使できません。
退職者には時季変更権が行使できない
しかし、退職する社員に対しては、この時季変更権を行使することができません。なぜなら、退職により残っていた年休は消滅するため、退職日以降に振り替える日が存在しないからです。
つまり、法律上は連続で年休を取得させなければならないということになります。
実務的な解決策
ただし、杓子定規に法律論だけで考えていては問題は解決しません。以下のような対応が有効です。
1. 話し合いによる解決 会社側の事情を説明し、引き継ぎのために出社が必要な日を設ける話し合いを行うことが重要です。多くの場合、労働者も円満退職を望んでいるため、合理的な提案であれば協力してもらえることが多いものです。
2. 就業規則での事前対策 このような事態を予防するため、重要な職務については引き継ぎをする義務があり、これを怠って退職することは就業規則違反とする規定を設けておくことも有効です。
3. 退職日の先延ばしは避ける 年休を100%消化させるために本来の退職日を先延ばしすることは避けるべきです。このような処理を認めると、他の社員への悪影響が心配されます。
問題2:残った年休の買い取りは可能か?
原則:年休の買い取りは禁止
年次有給休暇は、労働者の身体・精神の健康維持が目的とされています。会社が買い取りを認めることは、労働者が休暇を取る機会を奪うことになるため、原則として年休の買い上げは許されません。
例外的に買い取りが認められる3つのケース
ただし、以下の3つの場合には例外的に買い取りが認められています。
例外1:退職により失効する年休 業務の引き継ぎなどで年休の消化が困難な場合、残日数について買い取り処理をすることで対応できます。これが今回のケースに該当します。
例外2:時効により消滅した年休 年休は発生から2年で時効により消滅します。この時効消滅した年休については買い取りが認められています。
例外3:法定を上回る日数の年休(法定外年休) 労働基準法では6ヵ月継続勤務で10労働日が法定付与日数ですが、就業規則で13労働日与えている場合、超過分の3労働日については買い取りが認められています。
買い取り価格に決まりはない
例外的に年休を買い上げる場合の金額には、特にルールがありません。就業規則で定めればその価格によることもでき、必ずしもその労働者の賃金に基づく必要はありません。定額1万円でも問題ありませんし、特別手当として支給することも可能です。
重要な注意点:買い取りは会社の義務ではない
ここで特に注意していただきたいのは、買い取りは例外的に認められる処理であって、労働者に法律上当然に認められる権利ではないということです。
退職する従業員から未消化の年休の買い取りを求められて困っているという相談をよく受けますが、就業規則等に買い取りについて特段の規定がなければ、従業員からの買い取り要求に応じる義務は会社にはありません。
事前準備と柔軟な対応が鍵
退職時の年休問題を円滑に解決するためには、以下のポイントが重要です。
- 事前の就業規則整備:業務引き継ぎ義務を明確にしておく
- 早期の話し合い:退職が決まったら速やかに年休消化と業務引き継ぎについて相談する
- 柔軟な対応:法的原則を理解しつつ、実務的な解決策を模索する
- 一貫性の確保:他の従業員への影響を考慮し、一貫した対応を心がける
年休の問題は、労働者の権利と会社の事業運営の両方に関わる重要な問題です。法的な知識を持ちつつ、建設的な話し合いを通じて双方が納得できる解決策を見つけることが、円満な退職につながります。
不明な点がございましたら、お気軽に社労士の小椋にご相談ください。
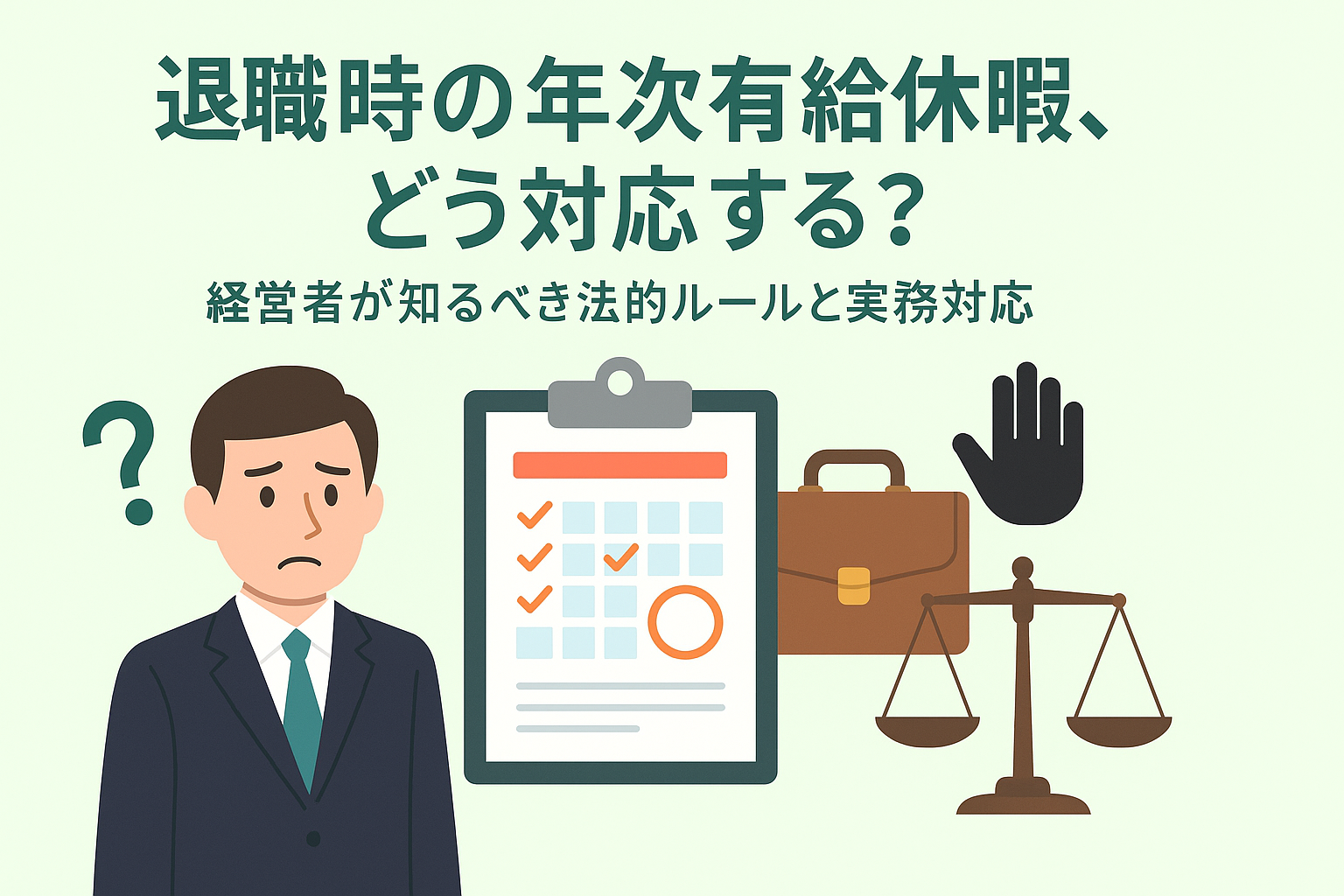

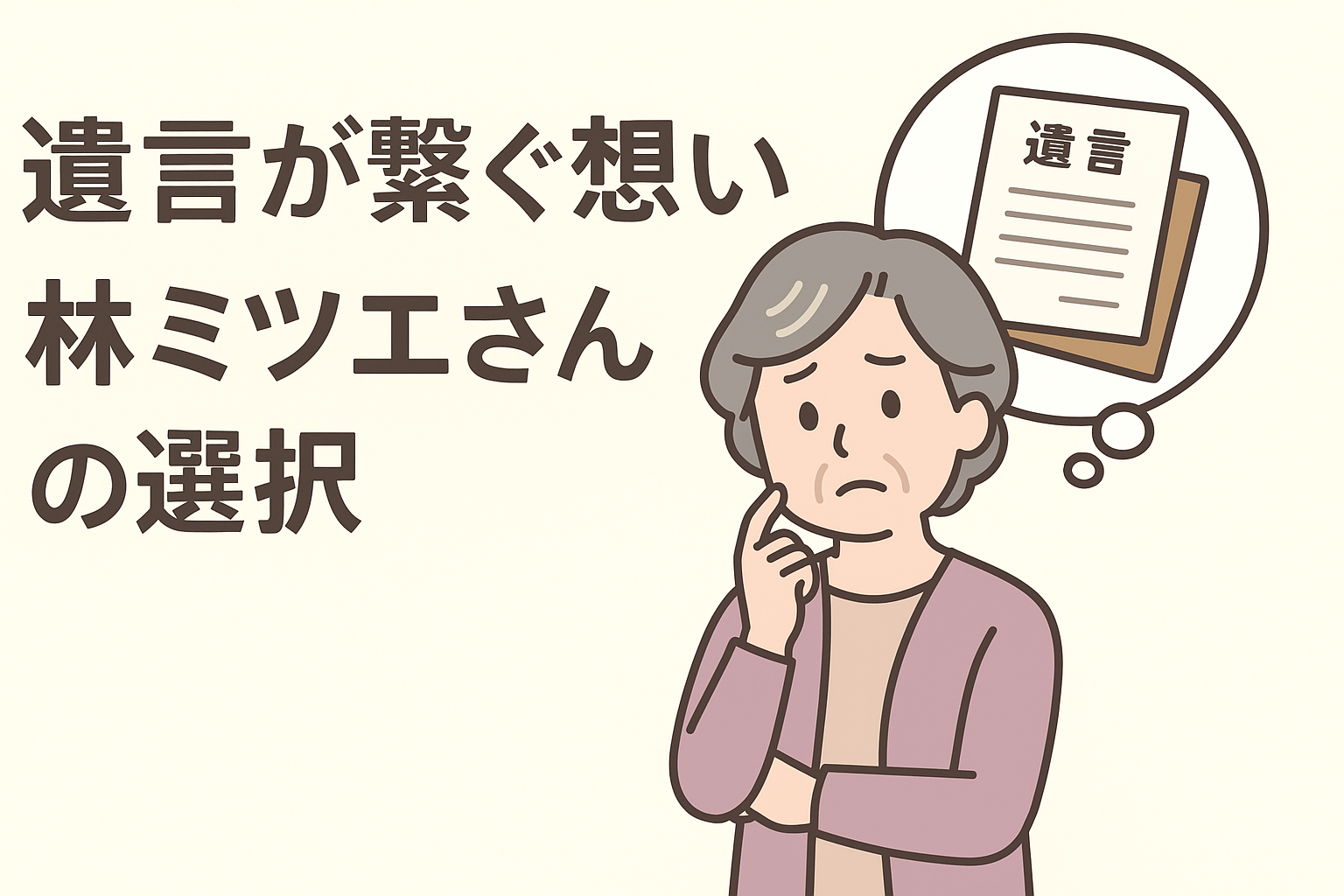
コメント