ある家族の相続トラブル実話
こんにちは。司法書士の小椋です。26年以上この仕事を続けていますが、相続の現場ほど、人間の本質が現れる場所はないと感じています。
今日は、私が実際に関わった事例をもとに、相続トラブルの実態についてお話しします。
発端 ― 突然の訃報
田中家(仮名)に相続の問題が持ち込まれたのは、父親の突然の訃報からわずか2週間後のことでした。
長男の誠さんは、弟の健太さん、妹の由美さんと葬儀後の整理を進めていたとき、父の書斎から一通の古い手紙を見つけました。そこには、父が若い頃に別の女性との間に子どもがいたことが記されていたのです。
「兄さん、これって…」
健太さんの震える声。三人の表情から血の気が引いていきました。
よくある相続トラブルのパターン
私のもとには、毎年数十件の相続相談が寄せられます。その多くは、『争族』という言葉がぴったり当てはまるような、心苦しい状況です。
田中家のように人間関係に問題があるケースは、決して珍しくありません。
感情的な対立を生む典型的な原因として:
- 過去に非行やお金のトラブルがあった相続人がいる
- 再婚相手やその子どもとの付き合いがない
- 認知されていない子どもの存在が判明する
田中家の場合、隠し子の存在が明らかになったことで、状況は一変しました。その方が認知されていたかどうかで、そもそも相続人になるのかという根本的な問題が発生したのです。
水面下に潜む不満
しかし、相続トラブルは必ずしも劇的な事情から始まるわけではありません。
田中家でも、隠し子の問題とは別に、兄弟間に長年の不満が蓄積されていました。
「僕は跡取りだからって、いつも父さんから特別扱いされて…」と誠さん。
「私たちは何も言わなかったけど、お兄ちゃんだけ大学院まで行かせてもらって、私は短大だったのよ」と由美さん。
「それに、お父さんの最期の5年間、毎週介護に通っていたのは僕と妻なのに」健太さんの言葉には、やりきれなさが滲んでいました。
生前の贈与や介護の負担 ― これらは法律用語で『特別受益』や『寄与分』と呼ばれ、相続の取り分を調整する際の重要な要素になります。
遺産の分け方という現実問題
感情的な対立に加えて、田中家にはもう一つの大きな問題がありました。遺産の大半が、父親が住んでいた自宅不動産だったのです。
誠さんは言いました。「僕はこの家で育ったし、父の跡を継ぐつもりだから、この家は手放したくない」
民法では法定相続分が定められていますが、不動産は現金と違って簡単に分けられません。
誠さんが自宅を相続すると、評価額は法定相続分を大きく超えてしまいます。公平に分けるには、他の兄弟に『代償金』を支払う必要がありますが、誠さんにはそれだけの資金がありませんでした。
「じゃあ、家を売却して現金で分けるしかないね」という由美さんの提案に、誠さんは激しく反発しました。
「待ってくれ。何か他の方法があるはずだ…」
こうして話し合いは膠着状態に陥りました。
司法書士として伝えたいこと
相続の現場で26年以上見てきた私が、皆さんにお伝えしたいことがあります。
相続トラブルの根底には、感情的な対立と経済的な利害の両方が絡み合っています。どちらか一方だけを解決しても、問題は終わりません。
重要なのは:
- 法律で自分が主張できることを正確に理解すること
- 相手の立場や事情にも耳を傾けること
- 最終的な落とし所を冷静に探ること
田中家の場合も、数回の話し合いと専門家の助言を経て、最終的には誠さんが銀行から融資を受けて代償金を用意し、健太さんの介護貢献を寄与分として評価することで、何とか合意に至りました。
皆様にお伝えしたいこと
相続は、故人が残した最後のメッセージであると同時に、残された家族の新しいスタートでもあります。
「争族」にならないために、生前からできることはたくさんあります。遺言書の作成、家族との対話、財産の整理…。
そして何より、日頃から家族との関係を大切にすること。それが最大の相続対策かもしれません。
司法書士小椋より:
相続でお困りの際は、早めに専門家にご相談ください。感情的になる前に、冷静に法律的な選択肢を知ることが、円満な解決への第一歩です。


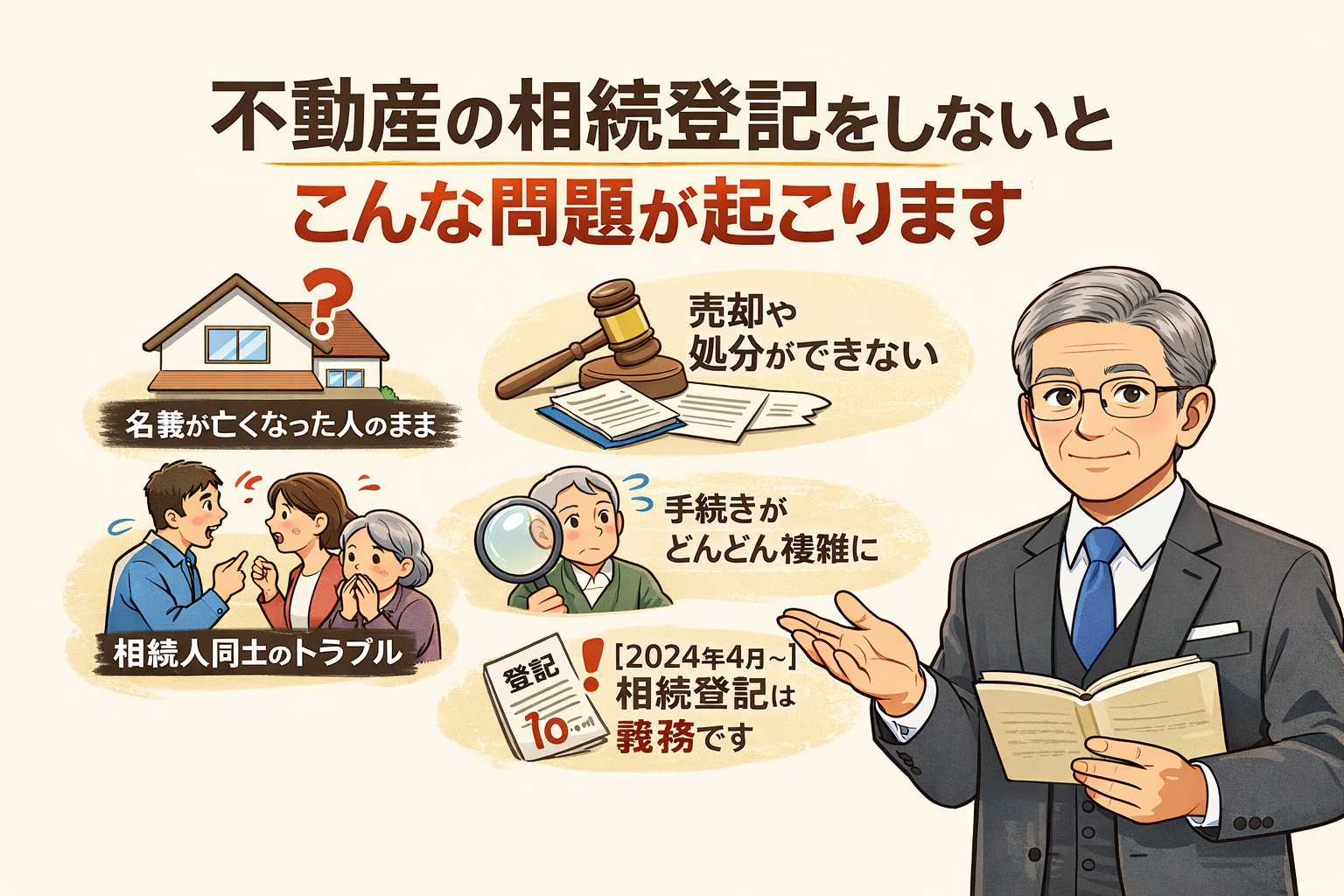
コメント